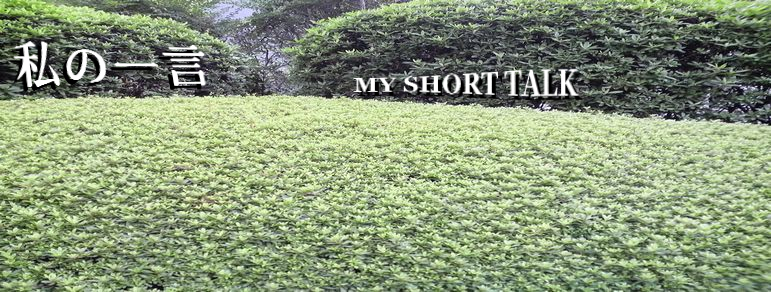 |
||||
| |
||||
| ヒバ林物語―第2部(佐井村の日本一のヒバの森)
|
||||
127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密 (自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん ―その2 2025/1/29 94.第三者委員会 という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が 宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ 家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない 広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
その3:所有権をめぐる投資家と林野庁の対立 25年1月30日 「130番はヒバ林だ、騒動の勃発」 昭和35年に18代源八が地元牛滝部落の中西氏に130番の3と4の移転登記をしてから7年がたった昭和42年になり、突然、その後の長い裁判闘争に繋がる事件が生じます。沢田恭助氏(岩手県議会議員との情報を得ていますが確認は取れていません)が、中西氏から字牛滝川目130番の3と4の移転登記を得、「旧土地台帳付属地図によればこの130番の土地は、堂の上の土地ではなく、類まれな美林である石山沢のヒバ林である」と言い始めたようなのです。堂の上の土地を購入しその結果として130番の移転登記を得ていた中西氏の方は、『払ったお金を支払ってくれるなら(堂の上の)土地を戻していい』として移転登記に応じたということのようです(判決文によります)。 この沢田氏の動きにより牛滝は風雲急を告げることとなるのですが、その前に、改めて1月17日の投稿で添付しました旧土地台帳付属地図を見ていただきたいと思います。牛滝部落は牛滝川の河口部分の狭い土地に偏っており、その他には南東に伸びる牛滝川とそれに沿って走り内陸の野平へ続く古くからの道(現在は国道338号線にとって代われています)があるだけで、その他の場所は全て山です。公図上では字牛滝川目という字は、この旧道の上下(北東と南西)に広がっています(途中までは並行して走る牛滝川の上下でもあります)。そして、こうした状況は江戸時代以降数百年もの間基本的に全く変わっていないのです。そうしたことを前提にして、旧土地台帳付属地図を見れば、誰しもがこの130番の地番は牛滝港から牛滝川に沿って走る旧道をしばらく行ったところの南西側にある(すなわち石山沢の西岸のヒバ林)と判断するはずとおもわれます。ところが、それまでは坂井家の人たちも牛滝住民の中西氏も旧土地台帳付属地図を見るようなことはなく、字牛滝川目130番の公図上の記載状況やその配置場所を意識していたのは地元の営林署職員くらいのものだったわけです。そうした事情から、中西氏へ移転登記がなされてから7年にもわたり、この過誤登記に起因した問題は何ら表面化しなかったというわけなのです。 25年1月31日 「突然有名になった牛滝のヒバ林」 18代源八の死後3年ほどして、それまでとは全く異種の人、すなわち堂の上の土地ではなくヒバ林に関心のある人が、字牛滝川目130番の登記を取得したことから大問題が生じることとなります。 一体いかなる経緯から沢田氏が「旧土地台帳付属地図によると字牛滝川目130番という地番は、(部落の北西の)堂の上ではなく、(東南の)牛滝川の上流の支流の一つである石山沢にあるヒバ林だ」と言い始めたのか、全く不明です。しかし、趣味でこのようなへき地の公図を見る人がいるとは思われず、沢田氏は岩手県議会議員だったようですから、その関係で営林署に知人がおり、そのルートから「未だ決着のつかない牛滝のヒバ林だが、登記だけは第3者に移ってしまっており、かえって話が出来なくなってしまって困っている。」と言ったようなことを耳に挟んだ可能性が十分に考えられます。そこで、彼が登記手続きの誤りの可能性に気づき(ただ、その背景事情をどこまで気づいておられたかは不明です)、公図でそれを確かめたという辺りが真相ではないかと、私は想像しています。ただ、この点は最早永遠に知り得ないでしょう。いずれにしろ、沢田氏の言はあっという間に世間に広がったようで、その翌年には弘前市の土地家屋調査士の佐藤三郎氏がその当時において権利者を自称する人からの依頼を受けてこのヒバ林の測量をし、その面積が約56万坪であることを確認しています。彼が作成した測量図を添付いたします。リンク先は以下のとおりです。 http://www.monobelaw.jp/material008.pdf とても見にくいのですが、とても丁寧に測量がされたことだけは感じられます。普通は、山の測量でここまで正確性は求めないのではと思われます。それだけ、価値のある山ということであったようです。 25年2月3日 「投資家との対決の構図」 そして、ヒバ山の測量がなされた頃には、どこからか以前お話した昭和10年の毎木調査表が木材業界に出回り、このヒバ林が突如として「とんでもない宝の山」として話題をさらうこととなっていったようなのです。こんな資料まで出回れば、誰もがヒバ林を民有地であると信じても責められないところでしょう。 こうした動きに、地元営林署は大慌てをしたと思われます。大げさに言えば、元は坂井家との交渉事と言うローカルマターであったものが、突然全国区レベルの問題と化したのですから。ところで、この「営林署」と言う呼び方は便宜上のものであることをお断りします。佐井営林署というのはあったのですが牛滝営林署という役所はなく、後に佐井営林署は大間営林署に合体され、その後の平成の組織改正でいまでは下北森林管理署という組織の下に存在しているようです。いずれにしろ、当時牛滝にあったのはそうした組織の末端の出先機関であったところです。そして、私が地元営林署と言うときには、その出先機関を指している場合が多いのですが、内容によっては佐井営林署やその上の監督機関の場合もあるのですが、厳密にその使い分けをなしているものではないことをお断りします。 営林署としては、あくまで坂井家との交渉に良かれと思って、多分軽い気持ちで、インチキな移転登記を画策したところ、逆に、それによってそれ迄話をしていた坂井家ではなく、部外者・県外者の投資家が登場してきて、それまでの官民の境界問題を無視し、石山沢とそれを囲む山の峰までの一体の土地、要は佐藤測量士の作成した56万坪のヒバ林全てが130番の地番が意味する土地であると主張されるような事態になってしまったのであり、解決に向かうどころか争いが大きくなってしまったわけです。地元営林署内で「こんなはずではなかった」と大騒ぎになったと思われます。 25年2月4日 「作戦の岐路」 きっと、この時の営林署内の混乱は何かの形で書面化され半世紀以上たった今もどこかに保管されていると思われます。しかし、誰かが最近はやりの「公益通報」でもしない限りその中身は永遠に知り得ないことでしょう。 そうなると、あくまで推測するしかないのですが、理屈としては地元営林署は以下の二通りの対応策の中からどちらかを選択し、それにつき林野庁から承認を得ることを迫られたと思われます。 1) 一つは、本当の経緯を話し、130番の移転登記は自分たちがしでかした間違いで、売買されたのはあくまで堂の上の土地であると白状し、ヒバ林についてはこれまでのように坂井家と境界確認の交渉を続けたい、とするか 2) 坂井家は堂の上の土地を売却するために130番の登記を移しており、それはとりもなおさず字牛滝川目130番の登記が堂の上の土地であったことを意味するはず、と居直るか ここで、営林署、そしてその後においては林野庁も、玉砕戦法のように思われる作戦2を選択しました。このような選択をするにはものすごく勇気が要ったと思われます。おそらく敗戦覚悟のうえで、インチキなことはしていないと言い張ることのメリットを優先させたものと想像します。しかし、結果的にはそれにより大勝利を得てしまうのですが、その代償は敗戦と同じように、ことによるとそれ以上に大きなもの、となるわけです。 但し、この作戦決定に林野庁自体がどこまで関わっていたかは分かりません。地元営林署から「坂井さんは堂の上の土地を売却するとして130番の移転登記をしており、130番は石山沢ではなく堂の上の土地だと思えます」とだけ説明し、その裏に地元営林署の企てがあったことを話さなければ、林野庁は「これまで130番は石山沢のヒバ林との前提で交渉をしてきたが、それがそうでないというのなら、私有地はないことになりいいことづくめだ」と考えた可能性は残ります。ことによると、紛争の当初の段階では、林野庁も地元営林署の罠にはまっていたのかもしれないのです。 25年2月5日 「正面突破作戦の採用」 1月31日の投稿で触れました佐藤氏による測量に際しては、不思議なことに地元営林署から何らの阻止行動も注意すらもなされなかったようです。昭和の時代に佐藤氏が裁判で証人に立たれており、その証言録を公文書の開示請求で取得してみたのですが、「土地の境界は地元の人の話を聞いて確認した。」旨述べられているだけで、営林署のことは一切触れられていません。要は、昭和43年の測量に際しては営林署は何ら関わりを持とうとしなかったということなのです。 しかし、これは、その後の林野庁の主張である、「130番の土地は堂の上を意味し、この石山沢のヒバ林は明治以来127林班として林野庁が管理している国有林である」と明らかに矛盾しています。国有林の中で私人が勝手に測量をすることを黙認するということはあり得ない話のはずなのです。恐らく、この時点では、営林署は昨日触れた究極の選択問題の結論を出せておらず、どう対応するか迷いに迷っていたものと思われます。測量は1週間ほどで終わったようですから、迷っている間に済んでしまったというのが真相ではなかったかと思われます。しかし、その他の資料から推察すると、佐藤氏の測量の直後か遅くともその翌年である昭和44年には、地元営林署は対応方法の2を選択することを決断し、その旨を上部機関に報告しその了解を取得したものと思われるところであります。 |
|||
| アーカイブ 2026年 2025年 2024年 2023年 2021年 2020年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 |
||||