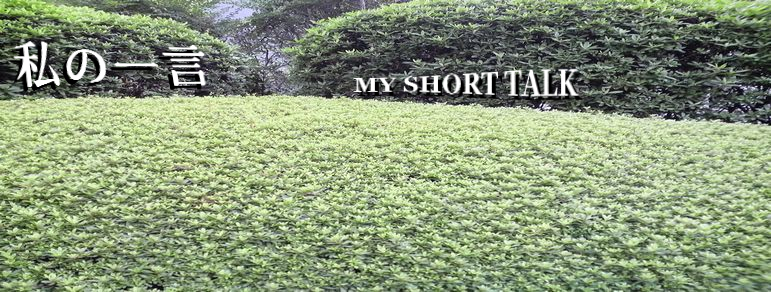 |
||||
| |
||||
| ヒバ林物語―第2部(佐井村の日本一のヒバの森)
|
||||
127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密 (自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん ―その2 2025/1/29 94.第三者委員会 という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が 宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ 家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない 広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
その6:明治の図面に昭和の測量技術 25年2月26日 「怪しげな古地図らしきもの」 実は、投資家が林野庁の主張する130番は堂の上の土地であるとの主張にまともに反論できない以上、投資家との裁判において林野庁の負はなくなったのですが、彼らのヒバ林への立ち入りを禁じるためには「ヒバ林は林野庁が管理する国有林である」との積極的な立証が必要となります。このために動員されたのが地元営林署の職員の証言であり、ヒバ林を含む一体の山林が国有林であることを示すとする土地台帳上の137番という地番であり、また、大正2年に抄本として作成された明治の官民境界査定図、それに古い林班図といった「古文書類」なります。いずれも怪しいことこの上ないのですが、職員の証言はさておいて、残りの書証類につき順次それらがどう怪しいか、偽物か、を解き明かしたいと思います。 まず、土地台帳で字牛滝川目137番というのがこのヒバ林を含む一体の国有林を示す地番であるとの林野庁の主張とそれを示すものとして証拠提出された土地台帳の写しを検討したいと思います。別紙がその写しで、リンク先は下記となります。 http://www.monobelaw.jp/material018.pdf この土地台帳を初めとしてこれらの証拠は、紛争の当初から出されていたのではなく、裁判所から「国の所有であることを示す証拠はないのですか」と催促されてから提出されたものと聞いています。問題は、裁判所に促されて提出された書面類が昔からあったもの(本物)なのか、裁判のために作り上げられたもの、偽造か、という点となります。添付の土地台帳の下部の所有主氏名欄には「官有地」との記載がありますが、その上の方に記載の「明治31年法律第32号により増徴地租」というのが曲者です。これは当時実施された租税の増額につき定めた規定であり、地租の対象となる私有地に対してのみ意味のある記述で、官有地に記載されるわけがないものとなります。恐らく、裁判用に昔の用紙を基にして急遽作成したのでしょうが、その際、良く調べずにこうしたあるべきでない記述を消し忘れたとしか考えられないところです。はっきり言って、営林署が偽造した代物なわけであります。また、そもそも国有地の土地台帳への登録というのは、土地台帳が私有地からの徴税のために整備されたものであることからして違和感が強いところです。それも付近の民間の字牛滝川目の地番の連番のような附番の仕方は不自然極まりないと思われます。ただ、このことについてはそれ以上には、今のところ私も解明できておりません。 25年2月27日 「境界査定図・境界査定簿」 次いで、裁判所でかなり決定的な証拠として認められた130番にかかる官民境界査定図を取り上げてみたいと思います。この写しは別紙のとおりでリンク先は下記となります。なお、林野庁は明治36年の査定図と主張し実際にはその後に書き直された写しを提出しているのですが、私の手元にあるのは大正2年に作成された抄本との記載があるもので、同じものと理解して間違いないと思われます。 http://www.monobelaw.jp/material010.pdf 一見すると、大正時代に作成されたもののように見えますが、実は、昭和の裁判の最中に堂の上の約1万坪の元は坂井家の土地を130番にするために作成された偽物となります。ただ、これをフェイスブックの形式的制約の中でかつ分かりやすく説明するのはさすがに荷が重く、一旦は、箇条書きで怪しげな要素を感じていただくことで良しとさせてください。では、それらを記してみます。
25年2月28日 「境界査定図・境界査定簿―2」 昨日、説明が煩雑になるのでとして直接私のネット記事を見ていただきたいとお伝えしましたが、少し乱暴だったと反省し「罠にはまった裁判−連載10」のリンク先を下記お知らせします。 http://www.monobelaw.jp/talkmonobe84.htm 無味乾燥な言葉の羅列で、読む気力を失われると思っています。ただ、このフェイスブックには、世間様に対する情報提供の意味があり、また、私にとっての備忘録としての意味もあることから、避けて通れないとご理解ください。 少し要点を述べますと、官民境界査定図は昨日の130番の査定図のように個々の地番につき作成されたものと、それらを字図面に落として字全体をカバーする形にしたもの(査定簿)があります。そして、裁判で提出されたヒバ林周辺の土地の官民境界査定簿は、昭和の国土調査の結果を基に昭和に作成されたものと断定せざるを得ない形状であることが明らかで、そうなると証拠提出された130番にかかる境界査定図も昭和の時代に作成、すなわち偽造、されたものであることの決め手となります。私のネット記事ではそのような不可解な周辺土地の査定図の形状の中から2例を取り上げて具体的に説明しており、分かりやすいと思われます。長くなりそうなので、その内容については次回にご説明したいと思います。 25年3月3日 「不可解な査定図の具体例」 偽造を示す例の一つ(131番)は、国土調査の結果により分筆され現在は131番の1と2に分かれている土地なのですが(ちなみに、この土地は石山沢を挟んでヒバ林の反対側にあります)、それが林野庁提出の境界査定図によると明治・大正時代において既に分筆がなされてしまっていることになっているのです。さすがに、あり得ないことが生じているわけです。偽造するならもう少し丁寧に行うべきだったでしょう。もう一つの例(132番)は、面積が以前の99平米から昭和の国土調査の結果を受けて40倍を超す4121平米と大幅に拡張されたのですが、それにもかかわらず、明治に作成されたはずの境界査定図の形状が昭和の国土調査に基づき明らかにされた132番の正しい形状と瓜二つというこれまた現実的にはあり得ないことが生じています。特に、この土地は起伏のある山岳にあるものなのでその形状の確定は平地よりもはるかに困難なはずですが、それをものともせずに明治の時代において正確無比な測量がなされ、かつ、面積の表示だけを40分の1に縮小したこととなってしまいます。いくらなんでも、それは無理でしょう。このように林野庁が証拠として提出した明治・大正時代に作成されたとする一連の境界査定図は、実際には、昭和50年ごろの国土調査を踏まえてそれに基づき裁判対策として作成されたものであることが明らかなのであります。 裁判では、境界査定図の氏名や書体についての疑問については、それらがその後において書き直されたものであるとしてある程度の相違が生じても致し方ないとの説明でその怪しさが大目に見られていたようなのですが、よくよく調べると、図面については書き直したのではなく、新たに創作した、というのがその実態であることが白日の下にさらされているわけです。 25年3月4日 「裁判官の立場」 ここで少しこうした事件を担当することとなった裁判官の立場を取り上げてみたいと思います。林野庁が国有林であることを示す書証を積極的に提示してきた以上、もし裁判官が「当初の移転登記は間違いでなされたようであり、付属地図を素直に見れば130番はやはり石山沢西岸のヒバ林の一部ではなかろうか」と林野庁の主張に対して疑いを持ち、最終的に130番がヒバ林を意味する(少なくともその一部)と認めることになれば、それは即、林野庁による古文書の証拠捏造・偽証を認定することにつながります。これは大変な勇気を要する大ごとであったはずです。林野庁の捨て身の戦法(バレたら全員身の破滅)が、裁判所をして戦意喪失させたと言えるでしょう。 この話しは間に関係者が入ったうえでの伝聞ですが、この裁判の法廷で、投資家の代理人が裁判官から「本気で役所が作成した書面(の信ぴょう性)を争うつもりですか」といった詰問を受け、代理人が慌てて「そういうつもりではありません」と答えさせられるという場面があったとのことです。それを見ていた裁判当事者の投資家はとても落胆したようですが、裁判官にとっては、官が嘘を言ったり偽造書面を証拠提出するといった認定をするのは命がけであり、直ぐに退官するだけの覚悟か、次回の転勤では根室地方裁判所網走支部への赴任を覚悟したうえでなければできなかったはずであり、同情せざるを得ないところがあります。要するに、裁判官としては、「この土地台帳付属地図はとんでもないでたらめ図面だ、と言い切り、その他の怪しさには目をつぶる他に身を守る術がなかった。」わけです。それがどんなに無理筋な結論であると分かっていてものこととなります。 25年3月5日 「矛盾」 官民境界査定図が偽造であることが明らかな以上、それ以上にこの書面につき議論をする必要もないところですが、仮にそれが本物だったと仮定すると、実は、今度はまた別の妙な問題を引き起こすことになります。当時の法制度・実務を直接調査する能力も気力もないことから、安直に、AIに「明治の官民境界査定の結果は土地台帳付属地図に反映されましたか?」と質問したところ、「はい」との回答を得ています。「その根拠規定を示してください」と重ねて聞くと、残念ながらあやふやな回答に終わってしまったのですが、常識的に考えて厳密な官民境界査定がなされてその結果が当時の付属地図と大きく違うのであればその査定図の結果が付属地図に反映される(要は、地図が修正される)とみるのが理の当然と思われます。それが全くなされずに昭和後期の国土調査まで修正されずに来たということ自体が、明治・大正には林野庁が証拠提出したような官民査定がなされていなかったことの動かせない証拠になると思われます(ただし、130番自体についてはいまだに手が付けられない状態)。一応参考までに、AIの回答書面のリンク先を下記に記します。 http://www.monobelaw.jp/material90004.pdf この点に関して、私には合理的な推測・判断は出来ても完全な立証は無理なのですが、この種のことに長けた人あるいは組織であれば、はっきりとした答えが出せるものと期待されます。多分、それは林野庁自身でありましょう。 なお、これはうわさ話的に聞いた話ですが、民事判決でヒバ林は137林班として管理されてきた国有林であり字牛滝川目130番の土地は堂の上にあるとの判決が確定した時に、地元営林署がその判決書をもって青森地方法務局むつ支局に行き、図面の修正を依頼したところ、「こんなものをトラック一杯持ってきても、(法務局としては)図面は変えられない」と門前払いを食らわされたとのことです。このことの意味を手短にお伝えするのは難しく断念するしかないのですが、翻って、明治・大正時代の官民境界査定図をその当時に営林署が役所に持って行ったのであれば、法務局(当時の税務署)は喜んで図面(付属地図)の修正に応じたことでありましょう。しかし、実際には、何故かそれがなされていないということになります。 25年3月6日 「土地所在場所の一斉移転の不可解さ」 裁判に証拠として提出された明治の官民境界査定簿は、問題の130番の査定図だけでなくその周辺にあったはずの他の全ての民有地も含んで字牛滝川目全体での官民境界を示しており、それら周辺土地の場所が全て大きく移動させられていることから、過去の裁判においても付属地図とのあまりの相違が問題として取り上げられています。この点を丁寧に指摘した裁判資料がありますので該当箇所のみを取り出し、リンク先を下記に記します。 http://www.monobelaw.jp/material90005.pdf 作成者は柏原語六弁護士で、書面は「鑑定書」と題され昭和51年の日付となっています。明治の境界査定処分の杜撰さ・不可解さを明らかにし、それを基に査定処分は無効とする意図で主張されたものと思われます。文章は参考程度に見ていただき、中の二つの図面に注目して下さい。図面で県道と記されているのは、私が旧道と言っている牛滝から野平に続く牛滝川沿いの昔からの道です。査定簿は、それ迄牛滝川に沿った旧道の南西側に位置していた民有地を、全て道や牛滝川の反対側の北東の地に移動させているわけです。付属地図に比してこれほど大幅な修正をなしたのに、そのことが当時においては一切付属地図に反映されず、昭和の国土調査に基づき、しかしまるで明治の境界査定処分の位置取りが正確であったかのように、民有地の位置が法務局の所管する不動産登記にかかる地図において移転されてしまっているわけです。 なお、この書面によりますと、これらの民有地の中には他の字への移動もなされたようですが、130番については位置は大幅に移動されたものの同じ字牛滝川目に所在するものとして記載がなされています。しかし、実際には、既に以前にお知らせしましたように、130番は字牛滝川目に接する字細間の端に移転させられているところです。要するに、堂の上の土地なるものの所在は、そもそもが字細間となります。 聞いた話ではありますが、国土調査に協力した山林の所有者たちは、代変わりしてその当時すでに自分の山林の位置につき確たる認識がなく、また、その場所自体には関心を持たず、営林署から提案された大幅に土地面積が拡張された修正登記案を喜んで受け入れたとのことです。 25年3月7日 「境界査定簿作成(偽造)の時期」 まず、一点訂正をさせて頂きます。2月28日の記事で、「裁判で提出されたヒバ林周辺の土地の官民境界査定図は、昭和の国土調査の結果を基に昭和に作成されたものと断定せざるを得ない形状であることが明らかで、そうなると証拠提出された130番にかかる境界査定図も昭和の時代に作成、すなわち偽造、されたものであることの決め手となります。」と指摘し、次いで、3月3日の記事において、「このように林野庁が証拠として提出した明治時代に作成されたとする一連の境界査定図は、実際には、昭和50年ごろの国土調査を踏まえてそれに基づき裁判対策として作成されたものであることが明らかなのであります。」と記しましたが、これには私の勘違いがありました。真相は、その逆でありました。 すなわち、以前にお知らせしましたように昭和43年の佐藤氏によるヒバ林の測量後、営林署はすぐに130番は堂の上に所在する土地であるとして全面対決する方針を固めたのですが、その為の対策の一環として、130番だけでなく、ヒバ林周辺の全ての土地を他所へ移動することが必要であると判断し、新たに境界査定簿を作成(偽造)することにしたものと思われます。そう考えると、そのような背景で作成(偽造)された官民境界査定簿に基づき、それとの調和を取るようにして昭和50年ごろに国土調査が行われたことになります。国土調査と言っても、国有林が大部分の山林の場合にはほとんど営林署が担当しているのと変わらず、両者がそっくりの結果になるのは、当然のこととなります。むしろ、明治の測量技術を勘案すると本来は査定図と国土調査の結果の間には相当なずれがあってしかるべきなのですが、それがそうなっていないわけです。明治の査定簿や査定図が昭和の国土調査の結果を先取りしたようなものであり、そのあまりの正確さがあだになり辻褄が合わなくなっているというわけです。 3月10日 「明治の境界査定簿と昭和の国土調査の関係」 先週末に、境界査定簿と国土調査の関係につき、以前の投稿に誤解があったことを説明しましたが、とても重要なテーマであることから、これに関しもう少し深く入り込んでみることとします。 3月6日の添付資料で明らかにされていますように、現在、国土調査の結果を踏まえた法務局の正式な図面としては、ヒバ林周辺の民有地は全て旧道の北側にあることとなっており、土地台帳付属地図とは真逆のものとなっています。そのことで裁判では投資家から「査定簿は怪しすぎ、無効」と攻撃されたわけですが、もし、130番だけが堂の上にあると主張し、その他の周辺の土地は付属地図の示す位置そのままに放置すると、そのことがそのまま国土調査でも確認され、土地台帳付属地図の上で130番の位置だけがおかしく、その他の周辺土地の場所は正しいこととなってしまいます。それでは、林野庁が苦境に立たされることになるのは必至です。裁判所から、「付属地図において、どうして、この130番だけが大きく場所を間違えて記載され、その近隣の土地は正しい位置で記載されたのですか?地図自体はよくできているのに、この地番だけが間違ってこの位置に掲載された理由は何だと思われますか?」と問われた際に、返答に窮するはずなのです。それを避けるためには、全ての周辺土地を移転させ、この付属地図は何というでたらめだ、とレッテルを張るしか他なかったわけです。 このように前後関係があべこべになったことから、私が客観的証拠として3月3日の投稿で取り上げた二つの事例の意味についても修正が必要となります。ただし、基本的には、明治に作成されたはずの査定図と昭和の国土調査の結果に基づく図面の完全一致という不可解点が問題の本質であることには変わらはありません。ただ、以前の投稿で述べた如くに「査定図は国土調査の結果に基づいて作成された」というのではなく、「査定図は国土調査を先取りして、その数年前に作成されたことを示すもの、すなわちそれらが偽造である」ことを示すものとして分かりやすい事例である、という説明に変わることになります。 こうした土地の全面移転により、裁判官に「この付属地図は完全にでたらめだ」と判断しやすい・言いやすい環境を提供したということになります。今70歳以上の方なら、昭和の時代に喜劇役者花菱アチャコが言った「メチャクチャでございまするがな」の名セリフを覚えておられるでしょう。本当に、やりたい放題であり、めちゃくちゃだと思います。この査定簿のめちゃぶりについては、後にヒバ林の刑事事件に絡んで再度触れることとします。 25年3月11日 「昨日の補足」 実は、初めて坂井三郎氏に会ったときに、佐藤氏によるこのヒバ林の測量の後すぐに営林署がその測量杭に沿って自分たちの杭を打ったという話を聞いていました。その時は、127林班の実態を強調したくてその補強証拠作りでやったのだろうとだけ理解していました。しかし、その時に営林署は、ヒバ林に杭を打つだけでなく、ヒバ林周辺の民有地全てを付属地図から大きく離れた場所に移転することをほぼ同時に計画していた可能性が極めて高いということのようです。ヒバ林については、本来は必要のないはずの林班の境界を示すものとして杭を打ち、その他の民有地については明治になされた境界査定処分として査定図を作成するための新規の杭打ちか現地に目印をしたこととなります。そして、その目印に従い昭和の技術を用いて実測し、正確な明治の境界査定図を作成し、後日そうした目印に従って国土調査がなされ、まるで神業であるかのように明治の査定図と称される書面の正しさを証明したというのが実態と思われます。 周辺民有地の所有者は自分の所有する山の場所や形状につきほとんど知識がなく、営林署の云われるがままに同意して国土調査を終えるしかなかったはずです。ましてや、大幅な面積拡大を得ているのですから、ノーという理由がないところです。 3月12日 「官を否定することの難しさ」 昭和・平成の裁判において、投資家サイドは、査定簿等は偽造ではなかろうかとの疑問を有していたはずですし、事実そのように主張した当事者もおられました。しかし、そこまで主張することは、現実的には林野庁に加えて裁判所も敵に回すに等しく、多数の投資家は妥協策として偽造とまではいわず余りにひどい間違い=無効なる主張を採用したようであります。このことは、3月4日の投稿でも触れたところですが、代理人の弁護士としては、官の不正を正面から指摘するのは困難が伴うところで、私も同情するところです。ただ、その時に、このような査定処分の結果に基づく土地台帳付属地図の訂正が何故なされなかったのかという林野庁の弱点を投資家が厳しく突いていれば、ことによると裁判の結果は違ったものになったかもしれないと悔やまれます。少なくともその流れを作るきっかけにはなった気がします。林野庁の捨て身の戦法に裁判所も投資家もしてやられたというところでしょうか。 完全な余談になりますが、これが米国のような陪審員裁判だと「水掛け論」にまで持って行ければしめたものなのです。陪審員がどう判断するかは誰にもわからないので、本格裁判に行くのは互いに怖く、和解が可能になるということになります。特に、かの国の国民性は、「公の組織はすぐに悪いことをする」との先入観がありますから。我が国では真逆で、官との争いが水掛け論になった瞬間に、即、敗訴となるわけです。我が国では、水掛け論で民が勝つことは予定されていません。民事訴訟法228条で、公文書としての形式の整ったものは基本的に正規(すなわち正しく)に作成されたものと推定されています。要は、制度的に官が裁判所を「罠に嵌める」などということは予想されていないわけです。その掟を破って官を弾劾するというのは裁判官にとっては荷が重すぎるでしょう。 |
|||
| アーカイブ 2026年 2025年 2024年 2023年 2021年 2020年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 |
||||