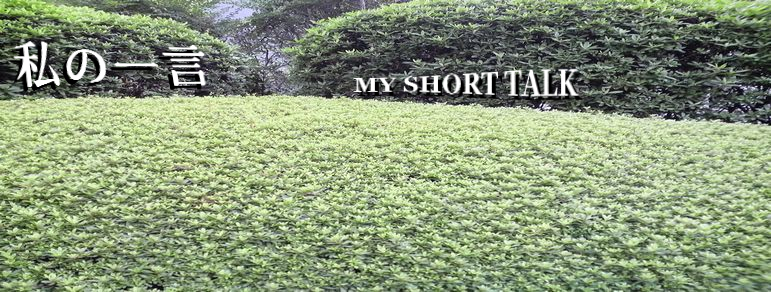 |
||||
| |
||||
| ヒバ林物語―第2部(佐井村の日本一のヒバの森)
|
||||
127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密 (自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん ―その2 2025/1/29 94.第三者委員会 という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が 宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ 家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない 広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
その5:土地台帳付属地図の欠陥? 25年2月17日 「土地台帳付属地図の欠陥」 そして、旧道を挟みヒバ林のすぐ北を流れている牛滝川が付属地図には載っていないことが林野庁に利用されてしまいました(1月17日の投稿のリンク先を参照)。普通なら、「川の記載が一部で漏れている」といった程度で済むはずのことですが、本件では付属地図全体の信頼性に難癖をつける格好の材料として大々的に利用されることとなりました。結論だけをお伝えしますと、このヒバ林の土地は、牛滝川の南側に位置するのは林野庁が指摘する通りなのですが、その間に牛滝部落と内陸の野平部落を結ぶ古くからの道があり、この旧道は明確に付属地図に書かれており、直接には牛滝川に接してはいないのです。公図においては、一般的に川よりも道の方が大切であり、ましてや地番に接しているのが道であれば川の重要性は2の次3の次となってしまいます。このことにつきましては、私が法務局のむつ支局に問い合わせてその回答を得ていますので、以下にリンクいたします。少し長文ですが、「牛滝川の記載がないから130番はヒバ林ではあり得ない」という難癖が、本来取るに足らないものであったことはご理解いただけると思います。 http://www.monobelaw.jp/material90002.pdf 何のことはない、公図はとても正確に野平への旧道や牛滝川周辺を示しているのですが、何の拍子かで牛滝川の流れの記載が一部抜け落ちていただけ、というたわいのない話なわけです。なお、この旧道は現在は国道338号線に取って代わられていますが、12月9日の投稿で触れましたように牛滝森林鉄道は戦後にこの旧道に沿って敷設されており、その面影は今も牛滝川に沿って残されているはずです。そして、飢餓海峡の犬飼多吉が通り抜けたあの道となります。 25年2月18日 「証拠価値を全面否定された付属地図」 どこまでが意図的でどこが結果としてなのかは分からないのですが、林野庁は投資家のジレンマに乗じて、正に「白を黒」と言い含めることに成功したという訳です。裁判官は、「何故、この付属地図の記載にはこんなひどい間違いがあるのだろう」と疑問は感じても、堂の上の土地取引で130番の移転登記がされたという中西氏の証言があり、実際に何年もの間中西氏が堂の上の土地を利用し多くの杉やヒバを植えたという実態がある以上、130番は堂の上の土地と判断するしかなかったわけです。そして、問題の付属地図については「とんでもなく出来が悪い」とのレッテルを張ってお終いにするしかなかったわけです。付属地図をけなしてその証拠価値を全否定する判決書の書き方はほぼ完ぺきに全ての事件において共通ですので、その内の一例のリンク先を記します。 http://www.monobelaw.jp/material90003.pdf 空疎な言葉の羅列です。バカバカしくて批判する気すら起きません。正直に、「中西証人の言によれば、130番の移転登記は堂の上の土地売買のためになされたものであることは明らかである。そうである以上、(私としては)土地台帳付属地図の130番の記載は大間違いと判断せざるを得ない。」と言ってほしかったところです。一言だけ言えば、牛滝部落周辺は山の間を牛滝川とそれに沿った旧道があるだけで、平地は集落のある河口の一部だけです。そこでの地図は、間違えたくても間違えようのないシンプルな形状なのです。 それでも、石山沢のヒバ林は坂井家のものであることは牛滝の住民全員が知っていたと言ってもおかしくないことであり、また2月7日に掲載した新聞記事から伺えますようにこの問題が地元でそれなりに有名な事件になっていた以上、彼らがどの様に動くかが裁判の行方を左右するポイントになり得たはずと思われます。しかし、不思議なことに、地元住民の声はほぼ皆無といっていいくらい、裁判資料からは出てきません。当時の佐井村の村長であった東出昇氏や渡辺幸定氏らはヒバ林が坂井家の所有であることをよくご存じのはずなのですが、そうした方の証言はなく、また何らの書面すら裁判所に提出された形跡がないのです。 25年2月19日 「何とも不可解な判決文」 付属台帳付属地図を非難する判決文は、当然その基となった林野庁の主張もほぼ同一なのですが、一体、「付属地図は、地図としてはほぼ正しいが、130番の位置が間違っており、本来は北東に2キロ以上離れた堂の上に記載されるべきもの。」と言っているのか、それとも「付属地図はそもそも地図としてでたらめで、全く役に立たない」と言っているのか、読めば読むほどわからなくなります。正直な私の印象を述べれば、まるで裁判官は「(判決を書くためには)この地図の証拠価値を否定するしかないが、そのためには、130番の記載場所がおかしいのか、地図として全体がめちゃくちゃだと言い切るべきなのか、判断がつかない。この際林野庁の主張に沿ってそれらをごっちゃ混ぜにしてケチをつけておくしかない。」と判断にしてわけの分らない判決文を書いたとしか思えないのです。まるで、子供が駄々をこねてしまったような判決と言いたいところです。実は、このようなわけの分らない判決がまかり通ってしまったために、それも一因となって、何時まで経っても投資家が諦めきれず、勝てるあてがないのに次から次へと裁判を続け、また、投資家間で権利(130番の登記)が転々と移転したという背景があります。 土地台帳付属地図の記載を唯一の根拠として裁判を戦っていた投資家としては、このような趣旨不明の判決を出されたのでは、諦めきれないのも無理はなく、同情したいと思います。私が、ことによると裁判所は罠にかかったふりをして、林野庁の欲しがった判決(130番は堂の上)を作成したのではと疑う所以であります。 25年2月20日 「村人の沈黙」 半ば推測、半ばは近時の営林署OBのつぶやきを耳にしたからなのですが、営林署は、「石山沢のヒバ林は坂井さんの山だと言うと、よそ者(投資家)に二束三文で宝の山を取られてしまうことになる。このことは絶対に口外しないように。」という御触れを出したようなのです。元々営林署は地元で隠然たる力を持っており、その営林署からよそ者に2足3文でヒバ林を取られてしまうといった説明を受けては、村人は、村長さんを含め、そして全てを知っている営林署の一般職員らも、黙りこくるしかなかったものと思われます。そのような閉鎖空間が出来上がってしまっていたわけです。平たく言えば、このヒバ林のことはその存在を含めタブーになってしまったわけです。そして、それは「公然の秘密」として今日まで続いてしまっているわけです。 このことに関して、とても面白い書簡があります。昭和45年11月14日の消印のある岩手県石鳥谷町(現在、花巻市の一部)在住の伊藤金市氏から源八の息子の弘氏に宛てられたものです。そこには、「ヒバ林」とか「石山沢」との記載こそありませんが、「山林解決には渡辺村長を初め竹内知事・現職責・・・全面的に応援するとのこと、又、佐井営林署も坂井さんとなれば示談しても良いとのことなそうですから・・・。」との報告がなされています。この書簡が出された当時は、2月6日の投稿でお話ししましたように、既にヒバ林につき投資家と林野庁間で民事裁判が争われており、そうした時に投資家との話し合いは出来なくても坂井氏となら話合いをしたいという地元営林署の本心が明らかにされているところです。私には、この書簡がヒバ林紛争の本当の中身が何であったかを余すところなく表していると思われます。営林署も林野庁も投資家との間のヒバ林問題を持て余していたのは間違いないでしょう。投資家との裁判に勝っても根本的には何も解決しないことを知っており、営林署としては本来の権利者である坂井家との話し合いをする必要を認識していたということになります。 この重要な書簡の封筒の表と裏の部分を添付します。リンク先は以下となります。もちろん中身の原本もありますが、それは他の類似の2通の書簡と同じくもうしばらく伏せておきます。 http://www.monobelaw.jp/material00703a.pdf 25年2月21日 「坂井家との交渉のとん挫」 昨日触れました岩手の伊藤氏の仲介になる交渉の件ですが、その後どのように進行したのか、全く分かりません。困り果てていた地元営林署としては何とか坂井家との話し合いでヒバ林の決着をつけたかったと思います。しかし、投資家との間の裁判が佳境を迎え、裁判に勝つためにはどうしても130番が堂の上の土地を意味すると主張せざるを得ないような流れの中で、地元営林署がヒバ林の真の所有者である坂井家と話し合いを進めたいと林野庁に打診しても、林野庁には「130番は堂の上の土地であり、坂井家はそもそもヒバ林の権利を持っていなかったということで始まった裁判じゃないですか。今頃になってそんな話を持ってこられても、もう遅い。」と言われ、取り上げてもらえなかったであろうと思われます。ましてや、以前のように坂井家とだけ話をしてそれで解決するものではなくなってしまい、本来第3者で権利のない投資家との関係もまとめなければならず、自らまいた種とはいえ、営林署は後戻りも坂井家との話し合いを進めることもできない状態に追い込まれてしまったと思われます。 そして、裁判の進行具合から、林野庁は、130番を堂の上の土地であると言いくるめられそうとの感触を得て調子に乗ってしまったのでしょう、過去においてこのヒバ林が私有地であると主張したものは誰もいなかったとまで断言し、裁判所の決断(誤審)を促しました。18代源八が読み書きができず、息子たちがヒバ林の経緯をほとんど聞かされていないことを知っていたからなのでしょうが、さすがにそれはやり過ぎだったというところです。過去において何もなければ、他の下北のヒバ林が丸裸に近く伐採されたのにこのヒバ林だけが手付かずに残されたことの説明が不可能になるはずなのです。坂井家の権利を法的に否定するだけでなく、過去の係争関係という事実自体までも否定したのですから、大したものです。しかし、このことが後に林野庁の首を絞めることとなります。坂井家のヒバ林に対する権利の痕跡を根こそぎ葬ろうとして、かえって墓穴を掘ったと言っていいでしょう。後に述べますが、裁判自体には完勝しても、林野庁はその後身動きの取れない状態に追い込められていきます。なお、読み書きができないのに地元の有力者との書簡のやり取りはどうしてできたのか、との疑問が出そうですが、源八の三男の三郎氏によるとそれらはすべて(後)妻を通じて処理していたということです。 25年2月25日 「しっかり者の『りそ』」 今から5年前に初めて坂井三郎氏とその子息の幸人氏に牛滝で会った際、「18代源八は婿養子で、読み書きができず、坂井家のことはすべて妻のりそさんが仕切っていた。」と聞かされたのですが、まさか本当に読み書きができないとまでは思わず、読み書きが不得手、ぐらいに理解をしていました。しかし、面白いものでこのフェイスブックを書くにあたり表面的な事実の裏に思いを致して小説家気取りでいろいろ考えていきますと、源八が本当に読み書きができなかったということがこのヒバ林事件において重要な役割をはたしていたことを理解できるようになりました。 恐らく、しっかり者で、17代源八の甥の子にあたるりそさんはほとんど坂井家のことを一人で仕切っていたと思われます。従って、18代源八は、石山沢のヒバ林についても「それが坂井家のもので17代源八が営林署といろいろやり合っていた。」といった程度のことしか知らされていなかったと思われます。その坂井家の中心にいたりそさんが戦時中の昭和16年に亡くなり、また、りそさんや源八が頼りにしていた長男の清一氏はそれより早く昭和10年に亡くなってしまっており、源八はりその死後は相談する相手もなくヒバ林問題への対応を迫られることになったと思われます。 このような源八ですから、自分で土地台帳やその付属地図を見たり登記簿を見るということはあり得なかったでしょうから、堂の上の土地を売却する際に飛内測量士に言われるがままに130番の登記を移転したのもよく理解が出来るところとなります。また、石山沢のヒバ林が坂井家のものとの認識はあっても、関係する資料を自分で読み込みそれ等を理解したうえで坂井家の権利取得の経緯を他人に説明するようなことは出来なかったと思われます。そのような状況ですから、当然、息子たちへの引継も何も出来なかったわけです。 しかし、年齢を重ね、何とかしなければとの思いから、1月24日の投稿でその書簡を掲載しましたように県の有力者に依頼してこのヒバ林の解決を託していたところ、その解決を見ずに亡くなってしまったという次第となります。私は、全体としてのストーリーを源八が読み書きができない人であったということを前提にして見直すことではっきりとその形が浮かび上がってくるように感じるところです。 |
|||
| アーカイブ 2026年 2025年 2024年 2023年 2021年 2020年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 |
||||