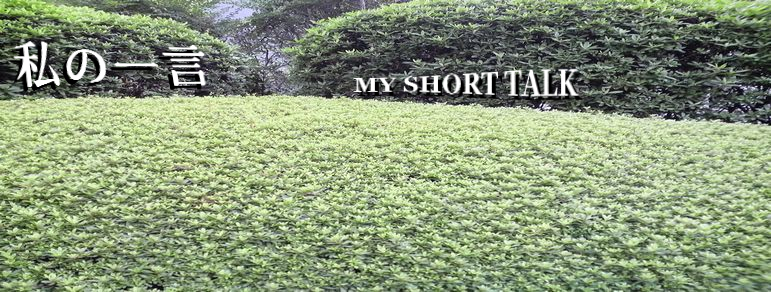 |
||||
| |
||||
| ヒバ林物語−第2部(佐井村の日本一のヒバの森) |
||||
127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密 (自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん ―その2 2025/1/29 94.第三者委員会 という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が 宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ 家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない 広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
その2:間違われた移転登記のその後 25年1月22日 「堂の上の土地が130番として売却される事になった経緯」 さて、堂の上の土地売買の話しに戻りますが、飛内測量士から堂の上の土地の地番を尋ねられた営林署の職員は、多分ですが、「今後の坂井家との交渉でこの登記がプラスになるかも」といった軽い気持ちで、堂の上とは関係のない石山沢のヒバ林の地番を移転登記させようと考えたもの思われます。ことによると、その職員が新人で全くの善意で間違ったことを伝えたのかもしれません。しかし、その際、地元営林署は130番=堂の上の1万坪の土地としてしまおうと欲を出してしまったようなのです。本来のヒバ林の形状に似せて堂の上の土地に国有林との境界を示す杭を打ってしまっています。このことは、土地取引の対象範囲を決めるために中西氏とともに現地に赴いた18代源八の3男にあたる三郎氏がそれを現認しているところなのです。その際、「なぜ、こんな杭があるのか」ととても不思議に感じたそうで、それで今も記憶にあるとのことです。ただ、その時は、三郎氏らはその裏にヒバ林の問題があるとは夢にも思っていなかったわけです。そして、時期は不明なのですがその後に一方的になされたこの境界杭に沿って大正時代に作成されたものとして営林署により官民境界査定図なるものが作成されることになるのですが、何とそれがバレることなく最後は最高裁までも欺いてしまいます。この経緯については、後に詳述することとなりますが、参考までに、この段階で、後の裁判で林野庁から提出された何時作成されたかも分からない字牛滝川目130番1と2の官民境界査定図をご覧いただきます。リンク先は、以下のとおりとなります。 http://www.monobelaw.jp/material010.pdf 25年1月23日 「間違った移転登記のその後」 そうした流れで、字牛滝川目130番の地番(3と4)の所有名義が登記簿上では地元牛滝の中西氏に移った後も、そのことは坂井源八と営林署間の交渉に何らの影響も与えなかったようです。当然ですが、土地売買の当事者にはヒバ林を売買したという意識は全くなく、従って、もしこの段階で営林署が「坂井さん、貴方は堂の上の土地を売却するために130番の地番を移されております。これまでの交渉の前提であった130番の土地が石山沢のヒバ林を意味するという説明が根拠を失いました。」と言い出せば、そこで大騒ぎになったはずです。源八は、「あの登記はあんたらの指導に従って、あんたらに任せてやったもので、ヒバ林とは何の関係もない。石山沢のヒバ林はうちの山だ」と言うでしょうし、中西氏も「石山沢のヒバ林を買ったのではなく、堂の上の土地を買ったもので、もし、この登記が間違っているなら直してほしい」という話になってしまい、話がまとまるどころから一段と紛糾したに違いありません。それまでのヒバ林の官民の境界の線引きの問題が吹っ飛んでしまい、all or nothingの問題に取って代わられるのですから、大ごとです。それでは、リスクが大きすぎ、坂井家との交渉を有利に持って行くための道具になるはずのものではなかったわけです。 25年1月24日 「坂井家と営林署の話し合い」 実際のところ、18代源八は、中西氏に堂の上の土地を売却し、登記簿上では字牛滝川目130番の3と4の移転登記を済ませた後も、営林署との間でヒバ林問題の解決を目指しており、1月10日の投稿で触れました県議会議員の三村泰右氏に加えて、地元で手広く山林業を営んでおられた工藤武智男氏にも営林署への口利きを依頼していたところです。昭和36年夏にその工藤氏から源八に宛てられた書簡が坂井家に残されており、そこには大要「この件から三村先生に下りてもらいたい。私の方の関係で話を進めさせて頂きたい」という趣旨が記されています。この書簡は、その消印から推測すると18代源八が中西氏に堂の上の土地を売却した翌年にあたる昭和36年のこととなります。ここで、このお二人の書簡の表紙と裏面を添付します。もちろん、中身もございます。 http://www.monobelaw.jp/material00701a.pdf http://www.monobelaw.jp/material00702a.pdf このフェイスブックを見られている方にとっては、それではわざわざ杭まで打って堂の上の土地を土地台帳付属地図の記す130番の土地にしてしまおうとした営林署の企てが何の役にも立っていないのでは、との疑問が沸くものと思われます。実は、本来は、その通りなのです。地元営林署としては坂井家との話し合いがうまく進まないことへの焦りから本来は何の効果もないような無謀な企てをしたに過ぎなかったところなのです。しかし、その後の展開でこの地番のインチキ工作がとんでもない効果を発揮することになり、果ては最高裁判所までをも見事に罠に嵌めることになります。軽い気持ちで悪戯のように行ったにすぎないこと、余計なこと、が後になってすごい効果を発揮することになるのですから、世の中何が幸いするか分かりません。ただし、最終的にはことがうまく運び過ぎ、営林署も林野庁も自身が手に入れたものを持て余すこととなるのですが、それには複雑な過程がありますので、おいおい説明をしていきたいと思います。 25年1月27日 「AIに聞いてみた」 この連載を続けているのは、何とかして「佐井村の圧倒的な日本一のヒバ林を世に知らしめたい」ということなのですが、週末に、AIとやりとりし添付のような返事をもらいました。まだ世間様には知られていませんが、AI にはある程度知ってもらっているな、と少しうれしくなりました。ただ、「著者自身の現地訪問」という指摘は、私がヒバ林に行ったことと朝日新聞の記者のヒバ林内への立ち入りが混同されているようなのですが、それはご愛敬というところでしょうか。 それで思いついたのが、AIというものにもう一段積極的にこのヒバ林を認識させることを今後の一つの目標にするということです。AIが何の拍子かに私のこの運動の応援をしてくれるかもしれないとの淡い期待です。逆に敵になってくれても、私としてはウエルカムなところです。AIの記事のリンク先は以下となります。 http://www.monobelaw.jp/material90001.pdf 25年1月28日 「18代源八の死去」 昭和30年代の三村氏や工藤氏による青森県の政界を巻き込んだ営林署ないし林野庁との交渉がその後どのように進んだのかは全く分からないのですが、昭和39年に18代源八が逝去してしまっていることから、何ら具体的な解決に至らずにヒバ林の交渉は頓挫してしまったようであります。と言いますのは、18代源八の跡取り的立場にあったはずの次男の弘氏には放蕩癖がり、源八からヒバ林にかかることの推移を聞かされておらず、交渉そのものが自然消滅してしまったようなのです。むしろ、弘氏は、源八の死後、昭和40年2月に札幌の横井茂氏に堂の上の残りの半分の土地を売却し、それに伴い130番の1と2の所有権移転登記をしています。そういうわけで、この時点で、坂井家が石山沢のヒバ林を所有していることを示す一つの有力な証拠である所有権登記が全て第3者に移転してしまったこととなります。 25年1月29日 「しばしの平穏」 このような不可解な変化があったのですが、購入者(中西氏と横井氏)はいずれも単純に堂の上の土地を利用したかっただけの人達ですから、登記の不備で困ることは何もなかったわけで、そもそもそこに不備があること自体を知らなかったわけであります。例えば、中西氏は、購入した土地に1000本以上のスギやヒバを植えたそうです。もちろん、弘氏も他の坂井家の人たちも本来石山沢のヒバ林を示す登記が、間違って、既に第3者に移転されているとは夢にも気づいていなかったわけです。こうした間違いは、土地台帳付属地図を見て、石山沢のヒバ林がどのように登記されておりそれが公図上でどのように示されているかを知らない限り気づきようがありません。ということは、石山沢のヒバ林に惚れてそれを購入したいと思う人が現れ、それが誰の所有なのかを確かめるためにまずは公図を閲覧して、それが「字牛滝川目130番」という地番であることを確認し、その上でその登記簿を取得・閲覧して初めてヒバ林が誰の所有かを確認することが可能となります。それによって、その購入希望者は「元の所有者が坂井家で、そこから中西さん(又は横井さん)に移転している」ことを知ることとなります。ただし、最初のヒバ林購入希望者が中西氏に連絡を取り「ヒバ林を売ってもらえませんか」と尋ねても、それに対して中西氏は「私はヒバ林なんか持っていませんよ」と返事をされるでしょうから、そこで登記に間違いがあるらしいことが判明するという流れになりそうです。実は、そうした人が現れない限り、この不可解な状況(未登記の土地が別の地番の移転登記でやり取りされている)は誰にも知られず、また、何の問題も起こさずにいられるわけです。もちろん、地元営林署はそれを知っていたのですが、彼らもそれに対して手が出せない状況であったということになります。 しかし、こうした状況が、昭和42年に一変することとなります。ちなみにこの昭和42年というのは私が大学に入った年となります。 |
|||
| アーカイブ 2026年 2025年 2024年 2023年 2021年 2020年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 |
||||