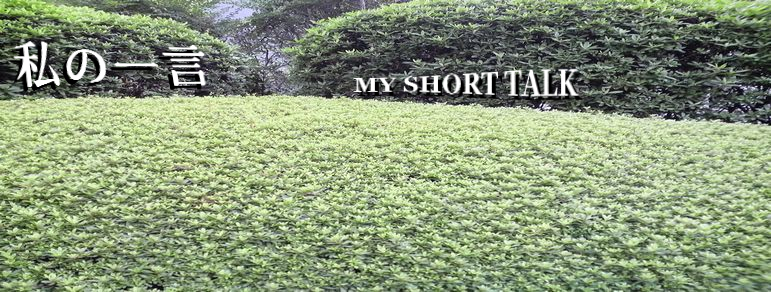 |
||||
| |
||||
| ヒバ林物語−その後(25年12月26日編) |
||||
127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密 (自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん ―その2 2025/1/29 94.第三者委員会 という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が 宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ 家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない 広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
25年12月10日 「牛滝川中流域にかかる清水橋」 本日は少し長たらしい投稿となります。まず地理的確認ですが、ヒバ林のすぐ北側を国道338号線が通りヒバ林の東側には牛滝川の支流の一つである石山沢が流れています。この辺りでは牛滝川の本体は338号線のさらに北側を流れているのですが、数百メートル海側に下ると清水橋という橋が架かっており、そこから海側では338号線は牛滝川の北側を走っています。これらを視覚的に理解いただくために、この辺りの国土地理院の地図を添付します。国道がヒバ林近くの2か所で川を渡っていることが確認できると思います。 http://monobelaw.jp/material90031.pdf 大枠としては、旧道と牛滝川の関係は現在の国道と牛滝川の関係に一致しているのですが、ここでひとつ興味のある事実があります。清水橋のすぐ海寄りに道路建設のために建設省が私人から取得した字牛滝川目145番25という土地があります。この土地は145番5から分筆されたもので元の所有者は坂井新之助さんという方なのですが、この土地は旧土地台帳でもほぼその辺りの位置にあるものとして描かれており、その土地の南側を牛滝川が走っています。少し注意がいるのは、昔はこの辺りでは牛滝川の南側を走る旧道本体と北側を走る脇道のような旧道の両者があったところ、昭和の国道は海寄りからこの辺りまでは牛滝川の北側を走り、清水橋を渡った後は旧道の本道をそのまま走り上牛滝橋(ヒバ林のたもと)に至っているということであります。 このことで私が何を訴えたいかといいますと、旧土地台帳付属地図は少なくとも清水橋の辺りまでは牛滝川との関係を含めて正しく記載していると言わざるを得ないだろうということであります。そしてそうであれば、牛滝川がこの清水橋の辺りを通過した途端に突然消えるわけがないのですから、その先のところでは本来旧道の北側を走っているはずの牛滝川の記載が付属地図上になくてもそれは単にその部分の川の記載が省略されているに過ぎないものであることが当然の帰結になるというところです。このことから導き出せる一つの結論は、国道の関係者(建設省)は、旧土地台帳付属地図は私有地の位置関係を正しく記載しているものとして清水橋やその周辺の工事をしていたことが知られるということになります。まだまだ説明が要りますが、長くなりますので今日はここで終了します。 25年12月12日 「清水橋の土地の重要性」 一昨日に引き続き、清水橋に関連したポイントに触れたいと思います。それは、清水橋以東の338号線は牛滝川の南側を走っており、旧土地台帳によれば旧道の南側には問題の字牛滝川目130番を初めとして数個の私有地があるのですが、これらの土地は、以前にお話ししましたように昭和50年前後の国土調査を利用して全て牛滝川の北西側へ移転させられてしまっており(130番は判決によって堂の上に飛ばされたのですが)、建設省はそれらの結果を利用して清水橋以東の338号線を国有地を利用して建設したものとして処理しているようなのです。半ばインチキですが、土地所有者がその扱い(場所の移転)に同意している以上、この点を直接非難するのは難しいところです。また、この145番の5は、昭和50年の国土調査を経ていますが、今も基本的に土地台帳付属地図が示すのと同じような位置に描かれているようです。要は、場所を移動させられていないのです。結局のところ、付属地図は海側から清水橋までは正しいと判断せざるを得ず、裁判所の肩をもってもあくまでそこから先のヒバ林の周辺の私有地の位置関係だけが間違とされるべきこととなります。きっと建設省からは「橋や道路の建設に必要な川の反対側(海側)にある私有地の処理にまでそちらのヒバ林紛争のもめごとを絡ませないでほしい」と頼まれたのかもしれません。恐らく、この理は佐井村の付属地図全般に該当するはずで、牛滝川の清水橋より上流周辺の私有林という特定の対象・場所のみが、裁判所により、検討に値しない杜撰な図面、として排除されているわけです。それらの私有地の配置換えは130番の土地を堂の上にありと認定をするための犠牲にされたと言えましょう。 前回と合わせて、とてもわかりにくい投稿となってしまいました。反省です。 25年12月15日 「付属地図の旧道と昭和の国道が示すこと」 先週の投稿はとても分かりにくく、お叱りを受けています。ただ、大切なポイントではありますので、さらに敷衍したいと思います。江戸時代から続く牛滝と野平を結ぶ旧道は道幅が1メートルほどのものであったと思われ、後戦後しばらくはそこにトロッコのような牛滝森林鉄道が走っていたことは既にお知らせしたところです(10月24日の投稿)。度々触れますように、その旧道こそ、映画「飢餓海峡」で三国廉太郎扮する犬飼多吉が内陸に逃げ込んでいった道となりますが、きっと映画監督はその時代設定当時において森林鉄道が牛滝にもあったことまではご存じなかったのでしょう。そして、森林鉄道の撤去後に、338号線の開設工事が本格的に始まったわけです。338号線は半島北端の大間からほぼ海岸沿いの崖の上を走って南下し字牛滝に隣接する字細間に入り、それこそ問題の堂の上の直ぐ近くを通って牛滝集落の東端に達します。その後は、牛滝川沿いにその北側をしばらく走り、前回お知らせした清水橋を越えてからは旧道と同じくヒバ林の北端を走ることとなり、上牛滝橋のところで右に折れて石山沢沿いに次の集落である野平を目指すこととなります。このように、清水橋から上牛滝橋の間の数百メートルの距離は、完全と言っていいくらい旧道と国道は一致しています。このことからも、付属地図に記載されたヒバ林の北端の道路がこの旧道であることは疑う余地のないところとなります(以前の投稿で示したかもしれませんが、このことに関しては青森法務局むつ支局から回答書面を頂いていますので、改めて以下にリンク先を記します。)。ましてや旧道と直角に交わるように流れる石山沢はちゃんと川として付属地図に記載されているのですから。白を黒というとはよく言ったもので、これほど疑問を挟む余地のない字牛滝川目にかかる地図を徹底的にコケにした判決はいかなる力学から生じたのか、と改めてその不可解さに恐れ入ります。戦前やいささか司法の独立性が危ぶまれる昨今のことならともかく、民主主義が一番謳歌されていた昭和後期の時代の判決ですからなおさらの感がします。 http://monobelaw.jp/material01202.pdf 裁判官が、どうしても130番はヒバ林にあっては困ると思ったのなら、もっと素直に、「付属地図は地図としてはとても立派で正確なようです。しかし、字牛滝川目130番という土地についてはここ(ヒバ林)ではなく2キロ以上離れた堂の上にあると裁判所としては他の証拠から認定せざるを得ないので、同土地の記載だけは間違っていると結論することになります。何故130番が間違ってヒバ林にあるように付属地図上で記載されているのかは、裁判所にも分かりません。」と判事すべきであったでしょう。それなら、林野庁も周辺の土地の位置をわざわざ移転させなくても済んだわけです。悪いのは130番だけとお墨付きが出たのですから。ただし、そうなると「面白い判決が出た」ということで大きな話題を生み、その時点で真相(移転登記の間違い)がバレた可能性が高いと想像します。本来続き番号で付される隣接地の地番が、一つだけ2キロ以上も離れた場所に飛ぶことなどということはありえないからです。長くなり過ぎました。 25年12月17日 「源流のない川と行先のない川」 最後にもう一度、土地台帳付属地図での川の記載をめぐる問題を取り上げてみたいと思います。裁判所のようにこの図面を全くのでたらめと言い出したら何の建設的な議論もできないのですが、字牛滝川目130番という土地の所在地はどこかという特殊な問題は除外し、普通にこの図面を見ると付属地図は全体としてはよくできておりただ牛滝川の上流地域における記載が判然としないところがあると評価すべきものになると思われます。既にお知らせしましたように、戦後に建設された清水橋の辺りまでは牛滝川も旧道も付属地図において正しく記載されていることが確認できるわけです。しかし、付属地図にはそのあたりから先の牛滝川の上流の記載が無いわけですが、まさか牛滝川が清水橋辺りにその源流・水源を有するとは考えられません。他方で、付属地図にはヒバ林の横に川が流れており、それは石山沢とみるしかないところです。そして石山沢は牛滝川に流れるしかほかなく、そうでないと石山沢がどこにも流れていく先のない川になってしまいます。川は山に発して海に注ぎます。時に湖のこともありますが牛滝周辺にはそのような湖はありません。牛滝川の記載の欠けている部分を補わないと石山沢は海に行けずに途中で消えてしまうわけです。実際の牛滝川本体は、昔から、河口から南東に伸びてこのヒバ林のたもとで三つの支流に分かれており、それらは北側から揚の沢、野平沢、そして石山沢と名付けられています。この石山沢という呼び名が明治までは「宇志多岐小川」だったことは以前の投稿でお知らせしているところです。付属地図はこの牛滝川上流の支流を描きながらその手前の牛滝川本流の記載を省略しているわけです。より正確に表現すると現在の清水橋あたりからこの支流に分かれる地点までの数百メートルの間だけが省略・削除されていることになります。でも、ただそれだけのことなのです。このことは付属地図の縮小版と原図を見ればさらに明確になるはずです。見にくいのですが付属地図の全体図のヒバ林の少し左上の位置に145という地番が記載されていることが確認できるところです。その辺りが後の清水橋の場所となります。改めて付属地図全体図とヒバ林周辺図のリンク先を下記に記しておきます。原図では道は茶色で川は水色で描かれているので間違いようがありません。さらにコメントを追加すれば、判決は「牛滝地区には牛滝川以外には(大きな)川はない」と認めており、図面上の川が牛滝川かその支流であることは疑う余地がないところです。これらの付属地図と先日投稿した国土地理院の現状を示す地図を見比べれて頂ければ、付属地図がいかに正確に描かれているかがよく分かると思います。牛滝川周辺の地理・地形は簡明過ぎて、間違いようがないのです。 http://monobelaw.jp/material90032.pdf http://monobelaw.jp/material90033.pdf 25年12月19日 「津軽と下北」 地図を見ると、青森はカニの詰めのように左右から半島が伸びています。右側の大きい爪が下北半島で左側の小ぶりの爪が津軽半島となります。今の青森県は岩手の北半分を含めて元は八戸を拠点とする南部藩が治めていたとのことです。その後、津軽藩が弘前を拠点にして分離独立し、徐々に力をつけ、戊辰戦争で早期に政府方について勝ち組に乗ることで最後まで幕府軍に付いた南部藩との間でその後の運命が完全に逆転し、元津軽藩の人たちが青森全体を仕切ることとなったそうです。それに絡んで、旧会津藩の1万を超す人たちが斗南藩と藩名を変えてやせ地しかない山がちの下北に藩替えさせられたという歴史もあるそうです。こうした歴史的背景があるせいか、今や、津軽と青森は同一にみられ、当然弘前もその中で大事な位置を占めることになります。そして、経済的にも文化的にも青森は西が先行し、東は取り残されて原発の処理候補地のような役を担わされているわけです。 特に、下北半島は、古くから流刑地とされるほどの辺境の地で、土地自体も痩せて作物の栽培に適さないことから、牛滝等の一部の地区で北前船の豪商が活躍した以外は、見捨てられたような地となったところです。それに比して「津軽平野」で知られるように津軽は農業に適しており、地理的にも下北より有利な立場にあったところです。今更証拠は集められませんが、斗南藩の窮状や元津軽藩関係者の勢力拡大を見ると、維新の後、県や営林署の多数の幹部を津軽藩出身者が占めることとなり、旧南部藩と密接であった坂井家が厳しい立場に追い詰められたであろうことがうかがえます。 全くの偶然ですが、つい先日、テレビ番組で通常の観光コースから外れた手作りのインバウンド向けの旅行企画として下北半島が取り上げられていました。流行歌の題名にも「津軽」はよく登場しますが下北はまずありません。普通には誰も行かない・行けないような所への旅行が売りというわけですが、当然のごとくに大間のマグロの一本釣りがメインとなっていました。そして、その次の見どころとしては牛滝のすぐそばにある奇岩で有名な仏が浦が選ばれていました。それを見て私は、「本当はそこからものの10分のドライブでこの日本一のヒバ林に行けるのだが」と思った次第です。佐井村は地元の有力な観光資源にフタをしていると言っていいでしょう。何とももったいない話です。 25年12月22日 「字牛滝川目なる字名の由来」 字名の接尾語として付される「目」というのは、一般的にその字の対象地が特定の形状の地域(特に、谷間)であることを示すために用いられるとのことです。牛滝川目という字名につきこの理を当てはめると、その字が、牛滝の集落地域ではなく、集落から先の山に挟まれた牛滝川という川の周辺にある地域を指すものとなります。そうであるからこそ、付属地図で字牛滝川目は牛滝川を真ん中にしてその両側に広がっているわけです。そして、旧道がほぼ牛滝川の川辺にあったことからこの旧道に沿った土地が描かれているとも言えるところとなります。それに比して、堂の上という土地は牛滝川からかなり離れています。牛滝集落自体には「牛滝」と「屋敷裏」という二つの字があるのですが、堂の上はそのどちらにも属さず、字牛滝に隣接する字細間に位置すると思われるところです。結局のところ、地番の連続性からしても、堂の上の位置からしても、字牛滝川目130番という名の付く地番の土地を堂の上と呼ばれる場所にありとするのは余りに無理があり過ぎるわけです。この字の明確な境界図は佐井村役場にあるはずなのですが、未だにうやむやになっています。困ったものです。 25年12月24日 「負け惜しみ」 もうすぐ今年もお終いです。まさかこのヒバ林事件がこれほど長引くとは思っていませんでした。フェイスブックでの事件の内容説明は今年の4月に終えており、その後は番外編と称してヒバ林物語の広報が主眼となっているのですが、今だに全く世の認知を得ていません。思い出すと、昨年の1月に最初の広報である「公然の秘密:幻の日本一のヒバ林」をネットに掲載した後、調査報告書形式での事案の分析書を数か月にわたりホームページに掲載し、それが一段落した後の昨秋よりはフェイスブック「ヒバ林の会」を立ち上げて広報に努めてきたのですが、効果のほどは惨憺たる状況です。その間に、関係する自治体の議員さんや有力な地元紙、さらには林業に関わる大学や研究機関あるいは個人にも直接資料を送りこのヒバ林への関心を声掛けしてきたところです。これまでのところ、そうした活動もサッパリ効果も反応も生んでおりません。 始めから覚悟していたことではありますが、ここまでくるとさすがに少し気落ちします。ただ、これだけのことをしたのに誰も何の対応もしようとしなかったということが、逆に、将来このヒバ林が世に知れ渡ることとなった際には、大きなブーメランとなって彼らに降りかかるであろうと信じています。もちろん、半分は負け惜しみです。ひたすらジャニーズ事件の経過に重ねて「日本のジャーナリズムはこの程度のもの」と自分を鼓舞するしかありません。 25年12月26日 「世に知られた公然の秘密はない」 今年最後の投稿となります。以前、グーグルで「公然の秘密」で検索しても椎名さんの有名な同名の歌ばかりでヒバ林が出てこないと愚痴をこぼしましたが、本日、それは当然で、公然の秘密でトップに出るものはそもそも公然の秘密とは言えないという何とも初歩的な真実に気がつきました。当たり前ですが、椎名さんの「公然の秘密」は言葉だけであり、そもそも公然の秘密とは何の関係もありません。そこへ行くとこのヒバ林は本物の公然の秘密、リアルな秘密であり、知れ渡っていたのではその名が泣くわけです。という訳で、何となくグーグル検索で初めの方に出ないことに納得ができました。 私がよく比較に使うジャニーズ事件も公然の秘密としては全く検索に引っかかりません。面白いもので、本物の公然の秘密は秘密である時期には表に出ず、それが知られるようになると公然の秘密ではなくなるのですから、これまた検索に引っかからないようです。公然の秘密というのは世に知られるようになるまでの仮の姿ということになりそうです。そう思うとなんだか勇気が湧いてきました。世に知られた公然の秘密というものがあるとすればそれはタブーと呼ばれるべきものなのでしょう。 よいお年をお迎えください。
以上が12月26日編
|
|||
| アーカイブ 2026年 2025年 2024年 2023年 2021年 2020年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 |
||||