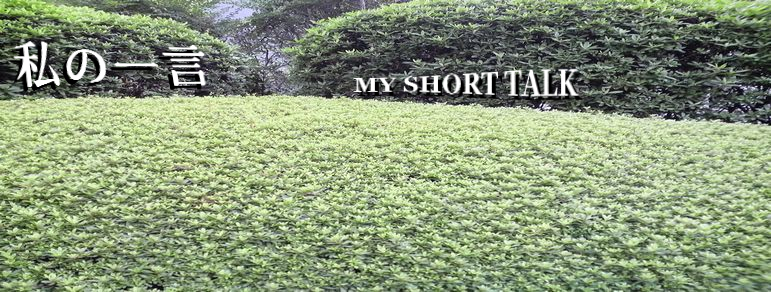 |
||||
| |
||||
| ヒバ林物語―第2部(佐井村の日本一のヒバの森)
|
||||
127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密 (自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん ―その2 2025/1/29 94.第三者委員会 という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が 宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ 家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない 広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
その4:後戻りできない裁判へ 25年2月6日 「後戻りできない裁判へ」 私の手元にある最も古い裁判記録は、所有権確認請求の上告事件の判決です(昭和52年(オ)第552号)。この事件は昭和45年に仙台高等裁判所に係属したということですので、それより前に青森地方裁判所にこの事件の提訴がなされたはずとなります。可能性としては昭和43年の6月の佐藤氏の測量の直後ごろの訴訟提起との推察が成り立ちそうです。おそらく、それ以上ずるずるするわけにはいかないとの判断であったと思われます。どちらが原告なのかはっきりしないのですが、多分、ヒバ林の伐採の動きを察した林野庁が原告になって立木の権利を購入したとする投資家に対して起こしたものと思われます。紛争の対象がこのヒバ林であり、その争点が字牛滝川目130番という地番が堂の上の土地を意味するのか石山沢のヒバ林を意味するのかである点はその後の同種の裁判と瓜二つです。この時点で、営林署・林野庁が腹を決め、後戻りできない法廷闘争に進むことを覚悟したものであることが知られます。 25年2月7日 「多くの裁判と複雑な権利変動」 それ以降、平成の始め頃にいたる迄数多くの同種裁判が多数の登記簿上の利害関係者と林野庁との間で争われることとなりました。中には投資家間の争いも多々あります。登記簿を見ると「仮登記」のオンパレードで、甲区欄には100を超す権利変動の登記がなされています。そして、それら全ての裁判で林野庁が勝たせてもらったわけです。ここからは、林野庁が如何なる論法・手段でこれらの裁判に勝訴し得たのか、また、何故、裁判所は林野庁を勝訴させたのか、その裏側を探っていくこととなります。これらのことを話し言葉で、かつ、このフェイスブックを見ていただいている方に読む気を失わせないような簡明な説明で進められるか、正直、自信がありません。それでも、誰にも知られずに佇んでいるヒバ林を世に出すためには「何故そんなへんてこりんな裁判がまかり通ったのか」を解き明かし一人でも多くの方の賛同を得なければならず、そのためにフェイスブックとしてこの物語を完結することが必要と考えています。そういった訳ですので、明日以降にその中身(罠にはまった裁判)に入りたいと思います。 ところであまり表ざたにならない民事裁判とは別に、伐採行為は(国有林の)森林窃盗にあたるとして刑事事件となるケースも生じており、そちらの方がニュースバリューがあったようで、その一例を示す青森読売新聞の記事がありますので、添付します。リンク先は以下のとおりです。素材が古くとても見にくいのですが、記事の扱いぶりからしてその当時(昭和52年)にはこのヒバ林事件は地元でかなり有名なものになっていたように思われます。 http://www.monobelaw.jp/material009.pdf 25年2月10日 「投資家の登記至上主義」 ここまでの記事を読まれた方は、林野庁がどうしてこれらの裁判で勝てた、すなわち、字牛滝川目130番という土地が堂の上の土地を意味するとの判決を得ることができたのか、不思議に思われると思います。実は、それがごく自然な判断のはずなのです。この不可解な結果を理解して頂くためには、まずは、中西氏や横井氏から堂の上の土地を買った投資家とその投資家からさらに買い受けた第2次第3次の投資家の思惑・期待がどのようなものであったかを知ることが必要となってきます。 沢田氏の動きを受けて、経済的価値の高いヒバ林、間違いなく日本一、を極めて少額の対価で手に入れられるという噂が急速に広がったはずです。そして、ヒバ林に興味もった投資家は登記簿と土地台帳付属地図の記載から字牛滝川目130番という地番が石山沢のヒバ林と確信したものと思われます。当然、現地に赴きその目でヒバを見たことでしょう。そこまではそれでいいのですが、日本の法制度では、地番(登記)はあくまで対抗要件というお守りのためのものとされており、平たく言いますと、それ自体が独立の価値・効果を持つものではないという基本原則があります。このことを多くの投資家が忘れてしまい、まるで「登記至上主義」なる原則があるかのように、その登記を得さえすればそれが本来反映している土地そのものが手に入ると誤解してしまったような面があるのです。ただ、最初に買った投資家から次に買い受けた投資家は、その地番が元は堂の上の土地売買に絡んで移転されたものであることを知らされていないでしょうから、「時価数十億円のヒバ林が、数百万円(ことによると数千万円)で手に入りますよ。登記面積は実際のヒバ林の50分の一程度ですが、仮にそうなっても安い買い物ですよ。」と勧められ、登記簿と公図を信じて130番の土地を購入したものと思われます。まさかとんでもない登記の間違いが先行しているとは夢にも思わなかったでしょう。ましてや、昭和10年の毎木表を見せられたら、「これは間違いない、宝のお山だ」、と信じ込んだのも無理もない気がします。しかし、当初の取引の実態が後の裁判では投資家の弱みとなり、一所懸命に戦っても所詮は勝てない立場に陥っていたのです。既に、理屈っぽい話に入り込みましたが、ここを避けては通れませんので、まずは、裁判における投資家の弱みとは何だったのか、さらにそのお話しをしてみたいと思います。 25年2月12日 「誰も自分が所有するもの以上を売却することはできない」 誰も自分が所有している以上のもの、他人が所有しているもの、を売ることはできません。中西氏も横井氏も、字牛滝川目130番という地番の登記簿上の所有者にはなりましたが、坂井家から取得したのはあくまで堂の上の土地であったもので、彼らが売却できるのはどこまで行っても自分たちが取得し所有する堂の上の土地だけです。その際、130番という地番を第3者に移転登記をしたとしても、それにより突然にその買手が、堂の上の土地ではなく、石山沢のヒバ林の権利を取得できるものではありません。これは、中西氏や横井氏が、自身で土地台帳付属地図を見て「130番は堂の上の土地ではなく、石山沢のヒバ林だ。」と気づいたとしても、同じこととなります。登記の間違いに気づいたからといってヒバ林の所有権が手に入るものではないことに何ら変わりはないところです。登記が間違っているだけなので、それを是正することはできますが、登記の間違いに乗じて別の土地の権利を取得することは出来ないわけです。 ということは、仮に字牛滝川目130番という地番が石山沢のヒバ林の土地を意味すると裁判所で正しく判断されたとしても、それは林野庁の思惑を挫くことにはなりますが、投資家のヒバ林に対する権利を認めさせるものにはなり得ないというわけなのです。この点が、投資家にとっては致命的な弱点だったわけです。しかし、何故かこのことが理解されずに不毛な裁判がなされ、逆に、その投資家の弱点を100パーセント利用したのが林野庁であり、ことによると薄々それに気づきつつ罠にはまったふりをしたのかもしれない裁判所に付け込まれたということになります。 25年2月13日 「対立の構図」 最初に投資家は勝てない闘いをしていたことをお話してしまい、それ以上の分析に興味を失われるかもしれませんが、投資家が負ける=林野庁の勝ちではないところがまた面白いところです。本来は、どちらも勝てなかったはずの争いが、裁判所が罠にはまったせいで林野庁が勝ってしまったというのが本件の真相となります。今後の説明を分かりやすくするために、手元にあった林野庁が作成したと思われるヒバ林と堂の上の位置関係を示す略図を添付します。以下が、そのリンク先です。 http://www.monobelaw.jp/material90002.pdf 一番上にある「位置図」は、下北半島における佐井村の牛滝部落の場所を示しており、その下の方で大きく「係争地」と記されたところが問題のヒバ林です。逆にその上の方に小さく「A土地」と記されている所が坂井家から中西氏と横井氏に売却された堂の上の土地となります。左手の縦の線は海岸線です。牛滝の前の海は平館海峡と呼ばれており、そこから少し北に行くと津軽海峡と呼称が変わるようです。この図面と以前添付した旧土地台帳付属地図を参照しながら、これからの説明を参考に林野庁のなした主張・立証が如何に欺瞞に満ちたものであったかをご理解いただければと思っています。 裁判での投資家の主張の根拠は、「旧土地台帳付属地図によれば、字牛滝川目130番という土地は牛滝川の上流の石山沢沿いのヒバ林であり、そこに疑う余地はない」の一本やりでした。それを補強するものとしては以前に触れた佐藤土地家屋調査士の手になる測量図が提出された程度となります。対して林野庁は怪しげな古文書を多数提出し、裁判所を罠に嵌めたわけです。 25年2月14日 「林野庁の主張の根拠」 投資家の主張に対する林野庁の反論の骨子は、?字牛滝川目130番という地番は堂の上の土地であり、?土地台帳付属地図の130番にはヒバ林の横を流れている牛滝川の記載がなく、石山沢のヒバ林を意味するものではなく、?ヒバ林は林野庁が定める行政上の区分で127林班と言う国有地でこれまで何人からもヒバ林につき権利主張を受けたことがなく、その地番は字牛滝川目137番であり、?130番につき大正2年に官民境界査定図の抄本が作成されておりそれによると同地番は堂の上の土地である、といったことを根拠にしたものでありました。それでは、これらの林野庁の主張の信ぴょう性を順次検証してみたいと思います。 最初に、130番は堂の上の土地を意味するとの主張を取り上げます。当然ですが、中西氏や横井氏が堂の上の土地を坂井家から買ったときに130番の登記名義が移転されていることがその根拠として主張されたわけです。この主張に対して、投資家側が、「それは営林署の指導に従って、間違ってなされたもので、本来、堂の上の土地は未登記なのだから、中西氏や横井氏への130番の移転登記という事実をもって同地番が堂の上の土地を示すということにはならない。坂井氏は、ヒバ林と堂の上の土地の両方を持っていたが、それらの地番についての知識はなかった。」との反論をなした形跡が、判決文を見る限りですが、見当たりません。おかしな話なのですが、以前にお話ししましたように、最初に「登記が間違ってなされていた」と認めてしまうと、「それではあなたはどうして2キロメートルも離れたヒバ林の権利を取得したのですか?」と問い詰められることから、反論したくても出来ないというジレンマに陥っていたというところでありましょう。また、多くの投資家は、当初の取引が堂の上の土地売買であったということすら知らなかったと思われます。そうなると、林野庁から「坂井氏は堂の上の土地の売買で字牛滝川目130番の移転登記をしている」と主張されても、それに反論する術がそもそもなかったと思われます。 こうなると、裏事情を知らされていない裁判所が、堂の上の土地売買に伴って売買当事者が130番の移転登記をしたのであるなら、130番は堂の上の土地を意味すると推論するのは極当然のこととなってしまいます。土地台帳付属地図については何とでもケチをつけられるということだったでしょう。これでは、始めから投資家に勝ち目がないわけです。 |
|||
| アーカイブ 2026年 2025年 2024年 2023年 2021年 2020年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 |
||||