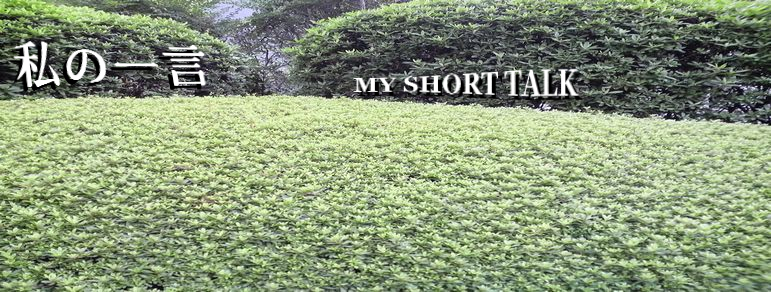 |
||||
| |
||||
| ヒバ林物語―第2部(佐井村の日本一のヒバの森)
|
||||
127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密 (自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん ―その2 2025/1/29 94.第三者委員会 という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が 宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ 家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない 広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
その9:平成の巌窟王 25年3月25日 「佐井村住民の立場」 不思議なのは、この牛滝川目の字図のような重要な証拠書面が裁判において投資家から提出された形跡がないことです。当時、村役場に保管されていたはずであり(本当は今も?)、それが何故顕在化しなかったのかという疑問です。それは、やはり、先日の投稿で述べましたように、いつの間にかヒバ林問題はそれが国有林かそれともよそ者の投資家のものかという図式に変容されてしまい、営林署から「ヒバ林は坂井家のものというと、よそ者にヒバ林を2足3文で取られてしまうぞ。」と脅された結果であろうと思われます。狭い閉鎖社会で、この営林署からのお触れは絶対的なものとなっていたと思われます。 以上で、一応は、このヒバ林紛争の謎を説明し終えたと思っています。ところで、以前、このヒバ林にからむ刑事事件につき触れていますが、「このヒバ林は本来坂井家のものであり、国有林ではない」として正面から争い、村人に対し営林署に反旗を翻すように鼓舞し、営林署の警告を無視してヒバを伐採した勇敢な人がおられます。森本操さんといい、坂井家に泊まり込んで古い資料を丹念に調べヒバ林が坂井家のものであるとの確信を得、営林署の所業に義憤を感じ、ヒバの伐採を強行されたものです。しかし、その頃には、既に、営林署がこの紛争への対応方法を「130番は堂の上の土地」として強行突破することを決めていたことから、直ぐに森林窃盗罪で告訴され、民事と瓜二つの理由で有罪判決を受け、懲役刑に処せられてしまいました。森本氏のすごいのは、自身の主張の正当性を信じるが余り出所後にも再度ヒバの伐採を行い、再度懲役刑を食らうこととなったことです。 25年3月26日 「平成の巌窟王」 とても不思議なのですが平成の巌窟王といってもいいようなこの森本操氏のことは全く如何なるマスコミにも取り上げられていないようなのです。 2月7日に投稿した青森読売の記事からして、せめて、「こんな馬鹿な人がいる」として社会面で記事にするのがマスコミとしての礼儀ではないかと感じるところです。おそらく、林野庁サイドから牽制球が投げられていたのであろうと推測されます。このヒバ林の件は、それにかかる民事・刑事の裁判沙汰の多さに比して、また、日本一のヒバ林がその中心にあるにも拘わらず、あまりに報道が少なすぎるのです。まるで戦前の報道規制がそのまま持ち込まれたのかと錯覚を起こすほどです。私の感覚ではそれが今に至るまで続いており、それがこのSNS発信の理由でもあります。 しかし、真相というものはバレるもののようで、森本氏は、服役中、刑務官から非常に丁重な扱いを受けたそうで、「貴方は無罪だから」とまで言われたとのことです。きっと、森本氏を不憫に思った営林署の職員がどこかで漏らしたのでしょう。残念ながら森本氏はつい先年亡くなったのですが、その直前まで無罪を訴えて東京地方裁判所に書類を送られていました。彼の名誉回復は直接私が約束したことでもあり、ここで触れておく次第です。 25年3月27日 「窃盗罪が成立するのか?」 追加で、森本氏の刑事事件につき、もう少しお話しをしたいと思います。犯罪は基本的に意図的なもの、故意犯といいますが、でないと成立しません。私は、森本氏の件を聞いた時から、そもそもこの件で(森林)窃盗罪が成立するのか、と疑問を持ちました。彼は、自分が切った木は国のものではなく、その所有者である投資家から自分が伐採の権利を買ったものと信じていたのですから、果たして窃盗罪が成立するのかどうか、疑問の余地があるからです。山で、シカと思って銃を撃ったら人だったとしたら、過失致死罪には問われることはあっても殺人罪に問われることはありません。森本氏の場合は、少し違っており、直ぐに答えは出せませんが、仮にヒバ林が国のものだったとしても、そこには法律家の言葉で言えば事実の錯誤なのかそれとも単なる違法性の錯誤なのかという問題がありそうなのです。しかし、そうした点が法廷で争われた形跡は全く無いようです。まるで、民事事件の結果あるいは流れそのままに有罪決着になってしまったようであり、私としてはかなりの違和感を覚える次第です。もちろん、彼がヒバ山で官憲の阻止行為に物理的に抵抗したのであれば、それは公務執行妨害に問われるでしょうが、起訴された罪名はあくまで森林窃盗なのが、気になるわけです。民事裁判では、ヒバ林が国有林かどうかで答えが出るのですが、刑事では、仮に国有林との認定であっても、それだけで即有罪とは断定できないはずです。「ヒバ林は国有林と認められるが、被告人はそれを自分が伐採権を有する私有林と固く信じて伐採・搬出に及んでおり、森林窃盗犯としては無罪」といった判決がなされる可能性が否定できないわけであります。どちらの所有か争いがあることを承知のうえで、そのリスクを踏まえて伐採したというのなら、未必の故意として処理されそうですが、森本氏の場合は国有林ではないと確信していたもので、相当にむつかしい問題があるはずと思われます。 恐らく、事前に何度も警告を受けていたのに官に逆らった罪人として処罰されたのでしょうが、乱暴に過ぎる気がします。ご本人がすでに亡くなってしまっており、今更感はありますが、もし、法的には森本氏は窃盗罪としては無罪であるべきだったのなら、今からでも彼の名誉を回復させてあげたいところです。もちろん、そもそもこのヒバ林が坂井家のものとなれば、当然ですが堂々と再審を申し立てることが可能なはずです。 25年3月28日 「営林署職員のつぶやき 最後にこの森本氏の関係で、別の意味で非常に重要で生々しいことがありますので、お話ししたいと思います。 森本氏が一時期佐井村の坂井家に住み込んでヒバ林に関する資料を調査していたことから、森林窃盗事件に関して坂井家が家宅捜査の対象となり、貴重な古文書類が押収されてしまい、それがそのままになっているとのことです。私の感覚からすると、確信犯として森林窃盗をなした森本氏に対する捜査において、何故、坂井家の古文書類が押収されたのか、大いに疑問があるところなのですが、この辺りを疑い始めると切りがありませんので深入りはしません。 実はそれよりも驚くべきことは、家宅捜索に来た営林署職員が、裁判で検察庁か林野庁が証拠として提出していた明治の官民境界査定簿の写しを見て、「これは・・・が手書きしたものだ」とポツリと発言したことです。この発言を聞いて、立ち会っていた坂井三郎氏は激怒したそうですが、職員は薄ら笑いを浮かべて帰って行ったとのことです。三郎氏の記憶では書いた人物の名は「ナルミ」という姓であったようですが、確実ではありません。「手書きした」との言葉は「偽造した」との意味と解されて致し方がないはずです。さすがに良心の呵責からつい本音が漏れたものと思われます。 もちろん、その場面のビデオテープはありませんが、それから40年ほどが経った令和の初めに、三郎氏の息子の幸人氏が親しくなった営林署OBから、「査定簿は、昔の字を書ける職員を捜して作成した。」と聞かされています。このOBの氏名の開示は今のところは控えることとします。できる限り迷惑をかけたくないからです。 その10:今頃になって分かった明治の分筆の真相 25年3月31日 「明治の地籍拡張と分筆登記は営林署との合作だった」 フェイスブックにあれこれ書いているうちに、これまで全く気づいていなかった重要なポイントがあることに、つい先日、気がつきました。それは何度もお話ししました明治27年の130番の現地測量・分筆登記にかかることです。私は、土地の分筆や地籍変更登記の専門家(土地家屋調査士)ではありませんが、地籍や境界を変更する際には、当然ながら、隣地の所有者の確認を得ることが必要なはずです。勝手に地積を大きくしたり小さくしたりできるというのでは隣地との境がわけの分らないものとなります。この130番で言えば、周囲は、北側が道路で、東側が石山沢ですが、西ないし南側は国有林と接しています。ということは、この地積の拡張・分筆をなしそれを然るべき役所(当時は税務署であったと思われます)に申請する際には、当然ですが、17代源八は隣地の所有者である国の承認を得ていたはずということになります。そうでないと、登記の変更もできないし、土地台帳付属地図の変更もできなかったわけです。1月17日の投稿で、「17代源八は、営林署と話がついたと思い、測量の上でこの分筆をしたはず。」と記しましたが、よく考えてみると国の承認がないとそもそも分筆登記・図面の修正そのものが出来なかった、税務署(当時の法務局)で受け付けてもらえなかった、ことが知られるところです。それもこの地籍の拡張は元の登記面積の数十倍であり、図面上のこととしてもそれだけ国の所有する山林面積が減ったことになるのですから。 以前の指摘は、経済合理性という観点からの常識ベースの推論だったのですが、実は、法的な手続き要件からして17代源八は地元営林署の了解を得たうえでないとそもそもこのような分筆登記は不可能だったことが知られます。何故、今までこんなシンプルなことに気がつかなかったのか、我ながら情けなくなります。話し言葉で書いていると、まるで口に出して話しているような感じになるのですが、それがかえって柔軟な思考を呼び込むのかもしれません。 これまで、私なりに調査をし、考えを巡らせ、本件の真相に迫ってきたつもりだったのですが、このような基本的なことに今頃になって気がつき、何とも落ち着きません。もっと他にも何か大事なことを見落としているのでは、と不安になってしまいます。 25年4月1日 「隣地の字牛滝川目129番の土地も移動させられている」 実は、元々旧道沿いの本ヒバ林の西北隣りには字牛滝川目129番という私有地がありました。ヒバ林全体からするとごくわずかな接面ではありますが、当時の付属地図上でれっきとした隣地として記載がされています。すなわち、17代源八は、明治27年の地籍拡張・分筆登記にあたっては、隣地所有者として、国だけでなく、129番の所有者の承諾を得ることが必要だったところです。このことをうまく説明するのが難しいのですが、土地台帳付属地図を改めてみますと、元の小さな130番の土地範囲を示す四角い囲いに接して129番が記載されていました。そして、分筆によって130番が大きくなり元の129番の土地を飲み込むようになったことから、分筆後には129番は大幅に北西にずらされた形で付属地図が修正されています。見にくいとは思いますが、このことを示す付属地図を2枚添付します。片方は分筆以前の状態が良く分かるものであり、もう一つは分筆後の129番の位置を示しています。リンク先は下記となります。付属地図では、修正がなされる際には元の記載を消すことなく、その部分の上に修正後の図面を張り付けるようにして対応していることから、こうした変化の跡が残されているところです。 http://www.monobelaw.jp/material90010.pdf http://www.monobelaw.jp/material90009.pdf なお、私も付属地図の現物を見たことはないのですが、かなり大きなもののはずで、その特定の場所(地番)の写しを請求すると、あらかじめ割り振られている対応する升目の部分が送られてきます。升目はA3の大きさで互いに少しづつ重なるようにできており上記の2つの図面もそのような関係にあります。 国有地は、付属地図に記載がないことからこうした変化が表に出てこないのですが、理屈としては129番の土地と同じ扱いを受けたはずのところです。肝心な点は、このような変更は130番の所有者である17代源八の一方的な意向だけではできないものであるということで、そこに疑問の余地はないところとなります。 このことからも、以前にお見せした林野庁提出の130番の官民境界査定図が隣地の地番として127番を記載していることの不可解さが知られることとなります(同図面の右下に小さくその記載があります)。付属地図が明示するように130番の隣地は129番なわけです。さらに言えば、129番の付属地図上の位置を大幅に動かす以上、129番の所有者もそれにつき隣地である国の承諾を得ていたはずとなります。 こうしてみると、明治27年の地籍拡張を伴う分筆は大事であったもので、坂井家と国との間の係争関係があと一歩で解決を見る寸前までいっていたことが知られます。残念ではあるのですが、皮肉にもそれがヒバ林を今日まで守ることになったところです。 |
|||
| アーカイブ 2026年 2025年 2024年 2023年 2021年 2020年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 |
||||