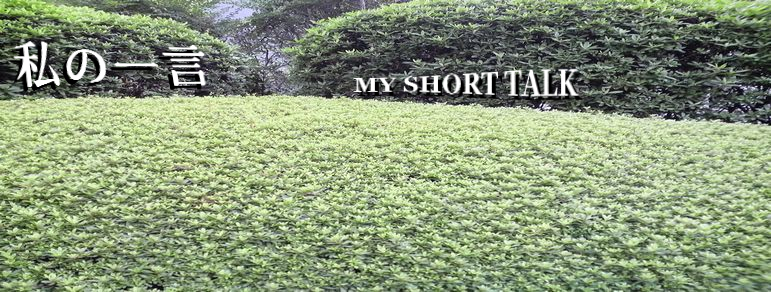 |
||||
| |
||||
| ヒバ林物語−その後(25年7月23日編) |
||||
127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密 (自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん ―その2 2025/1/29 94.第三者委員会 という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が 宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ 家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない 広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
25年7月7日 「奇跡か、それとも偽造か」 ヒバ林の横を走る338号線をそのまま北上しますと福浦という部落を通り厳しい肝がん沿いの山岳地帯に入ります。この辺りは海峡ラインとの名のある338号線でもその開設工事が最も難関なところだったようで、最終的には自衛隊の助けを借りて開通されたと聞いています。このヒバ林の件を長年調査している方がこの区間についての国土調査の地籍図と明治の官民境界査定図を入手しそれらを比較してびっくりすることとなりました。それらが瓜二つだったのです。まず、これら二つの図面を下記にリンクします。ただ、実物の図面はかなり大きくその一部を取り出していることと、査定図の縮尺が地籍図の縮尺の倍ぐらいになっている点をご注意ください。 http://www.monobelaw.jp/material90017.pdf 査定図 http://www.monobelaw.jp/material90019.pdf 上記に対応する地籍図 http://www.monobelaw.jp/material90018.pdf 査定図 http://www.monobelaw.jp/material90020.pdf 上記に対応する地籍図 その方は、私にこれらの資料を渡す際、林野庁は、牛滝周辺の明治の官民査定図を裁判で証拠提出していたので、この地域でも同じように明治の査定図がないと牛滝の書面が偽造であると思われることを恐れて作成したのではないでしょうか、との意見を伝えてくださいました。 そうした裏事情からの昭和の時代の偽造である可能性は十分にあるのですが、その前に、このそっくりな状況をどう評価するか、そのことの持つ問題点を広く皆様に知っていただきたいと思います。私の感覚では、測量機器も技術も稚拙な明治の時代に、昭和後期の座標軸を基にしたほぼ完ぺきな地籍測量の結果と全く同一の結果を得ていたとすると、それは奇跡かノーベル賞ものと称賛・自慢すべきものになるということです。皮肉ではなく、それだけでも、日本の土木・測量技術の歴史において特筆すべきことのはずです。当然、地元紙などは取り上げるべきでしょうし、ノーベル賞は無理でもギネスには合格すると思われます。ただ、ご覧いただくとお分かりのように、官民の境界がとても入り組んでおり、このような複雑の地形を測量を、それも急峻な山地で、明治に正確な測量が出来たとは、常識的にはちょっと信じられないところです。 さて、逆に、それが奇跡でも偶然でもなんでもなく、国土調査は、現地の測量を省略し、かなりよくできたと思われる明治の官民査定図の土地の形状をそのまま採用して長さだけを調整したもの、となると、今度は別の大問題が生じます。国土調査はそれまでの測量図の不十分さを一掃するために全国的に最新技術による測量を実施しようと意図されたものであり、昔の、ましてや明治の測量結果を丸写しするような作業は予定されていません。はっきり言って、完全な違法行為です。もし、リンク先の明治の官民査定図が本物なら、それをうのみにして現地確認を省いて地積測量図を作成した地元佐井村はその責任を問われることになるはずです。 ただ、牛滝のヒバ林に関しては、ヒバ林やその周辺の民有地を土地台帳付属地図の示す場所から大幅に移転させる必要があり、国土調査に先駆けてその移転先を示す官民査定図を明治の作として証拠提出する必要があったのですが、この地域でそのような係争があったとは思われず、林野庁は官民査定図に拘泥する必要はそもそもなかったところです。にもかかわらず、このような危険な橋を渡ってまで明治の作とする官民査定図を持ち出したのか、不思議でなりません。この資料を提供してくださった方が考えるように、牛滝と同じような官民査定図がないと後で問題になると考えたというのが答えかもしれませんが、どうも、すっきりしません。 今日は、不可解な図面の存在を指摘することで終えますが、とても大きな問題をはらんでいると思われるところです。それも重大な官の不正に関するものとなります。 25年7月9日 「ほめ殺し」 昭和の時代の話しですが、竹下氏が首相になる直前だったと思いますが、角栄氏との関係で右翼から「ほめ殺し」という手法で精神的な圧力を受けたことがありました。詳しくは覚えていないのですが、その当時結構な話題となりました。誰しも、大っぴらに、しかも誇張して褒められると気持ちが悪いと思います。ましてや、それが虚飾か皮肉に満ちていれば尚更でしょう。どうやら、地形の険しい下北半島での明治の官民境界査定はその当時に天才的な技術者が存在したお陰で昭和の最新技術に匹敵する正確さで測量図面が作成されたようであり、そのような官民境界査定図は我が国が誇るものとして国立図書館に時代を超えた高度な測量技術の実例として保管・展示されるべきと思われます。そして、それが叶ったときには、地元新聞に大々的にその記事を掲載してもらい、それを踏まえて正式にギネスブックに世界に冠たる19世紀の日本の測量技術として登録申請をなすことが期待されます。あるいは、ユネスコの世界遺産というのも考えていいかもしれません。 以上が私が考える本件の褒め殺し作戦となります。もちろん、登録申請をしたのちに、それがすんなり認められるか、登録委員会から図面の作成時期につき疑問が提起されるか、それは私にはわかりません。でも、とても楽しい展開になるのは間違いない気がします。裏の事情を知らない一般の人には、どちらに転んでも、愉快な話で終わりそうですから。 25年7月11日 「地域森林計画図の作成」 さて、不思議な明治の官民境界査定書の件は前回の投稿で一旦終了し、話を少し前に取り上げました林地台帳に戻したいと思います。先日、県の林政課企画グループから県が字牛滝川目130番1が所在する可能性があると推測する(地域)森林計画図の送付を頂きました。当然のごとく、その地図のどの辺りに130番1があると推測されているのかは不明でしたので、改めて、県がその所在場所である可能性があると考える場所を付記したものを送ってもらいました。それが下記のリンク先となります。赤の線で囲われた部分が森林計画の対象地でそれら民有地については個別に林地台帳が作成されますが、130番1があるかもしれないとされる場所は黄色の線で囲われており、森林計画の対象地でなっていないわけです。 http://www.monobelaw.jp/material90021.pdf ご覧いただくとお分かりのように、これらの図面は牛滝部落の北ないし東北方面を示しており、林政課はいわゆる堂の上に130番1が所在する可能性があるとの前提に立っているようであります。さっと見ても森林計画の対象となっている民有地よりも130番1の方が圧倒的に広いことが知られます。本来なら、当然、森林計画の対象になっているべきもののはずです。しかし、以前にお知らせしましたように、県は、「場所がはっきりしないのと国の所有か民間の所有か不明なため、130番1を森林計画の対象から除外している」と明言しているということになります。私は、県の担当官のこのような素直な対応についてはある種の感動を覚えました。「まだ、官も棄てたものではない。根っから腐っているわけではない。」と思った次第です。 25年7月14日 「林政課の素直な回答の意味」 先週末の続きとなりますが、県の回答が素直だからといってその内容が正しいというものではありません。そもそも県が送付してきた図面から知られますように、130番1の所在場所については、仮にそれが堂の上にあるとすればその具体的な場所につき不明確な点は全くありません。問題は、それが堂の上ではなく石山沢西岸にあるとの懸念があるために、所在場所が不明確という言葉になっているに過ぎないところです。厳しく言えば、所在場所が不明確というのはほとんど自己矛盾したような表現です。130番1の地番が示す山林は堂の上にあるか、または、そこから2キロ以上も離れた石山沢西岸にあるかのどちらかであり、あとはそのどちらを選ぶかという(政治的)判断の問題のはずです。それを場所が不明確という表現で県の林政課が対応するのは、場所については林野庁の主張する堂の上と坂井家が主張する石山沢西岸に見解が分かれており、県としてはどちらにも軍配を上げられない、と言っているに等しいところです。その意味では、130番1は石山沢西岸にある可能性もあるとしてその近辺の森林計画図に黄色の囲い書きをして送ってくれても良かったところです。さすがに、林野庁に遠慮してそこまでは踏み込むことができなかったものと思われます。 しかし、そうなると、何故、県林政課は林野庁の判断に従い130番1の所在場所を堂の上として林地台帳の作成に動かないのかが問題となります。やはり、その根底には林野庁の主張には納得しかねるとの林政課の本音があるとしか思われません。字牛滝川目130番1なる山林を地域森林計画の対象から外し、したがって同地番についての林地台帳の作成を不要とし、林野庁と県との間のこの地番の真の所在場所についての見解の相違を表面化しないようにしている、という辺りがことの真相でありましょう。この辺りを佐井村と歩調を合わせて対応しているというわけです。 逆に、そうではないとすると一体いかなる理由からこんな不可思議なことが生じているのか、サッパリ分かりません。このままでは、平成の終わり近くに林野庁の肝いりで創設された全国を網羅した民有林の総合的な地域森林計画構想が宙に浮いていると言えそうです。 25年7月16日 「県と村の重い口」 林地台帳の作成は、実質的には県が担っているようなのですが、特定の地番の場所やその所有者がどのように不明確かに付いての判断は制度上は地元の市町村がすることとなっているようです。このヒバ林について言えば、その所在地や所有者が不明というのは本来的には佐井村が判断すべきことで、県はそれを伝え聞いたうえで最終的にその場所又は地番を地域森林計画区の対象にするか否かを県として決定する立場に立っていると思われます。それで、私は、改めて、県の林政課に下記のような書面を送り回答を求めました。 http://www.monobelaw.jp/material90022.pdf 先日やっとこの質問につき電話で回答を得たのですが、歯切れば悪く、かなり古いことでありどの様な事情からの判断であったか分からない、といった回答で、明らかにそれまでの対応から後退しています。私がこのヒバ林にかかる裏事情を熟知したうえであえてこのような質問をしていることに対しての心理的な拒否感はあるでしょうし、私がこの件をあれこれフェイスブックに投稿していることも知っているのでしょうから、口が重くなるのは仕方がないと思います。直接、佐井村に村としての判断とその根拠を問いただした方がいいのかもしれません。でも、また同じような回答で避けられそうです。以前に触れましたように、昭和の時代の村長である東出氏や渡辺氏は、ヒバ林は坂井家のものとの判断をされていたと聞かされており(すなわち130番1は石山沢にある)、それに比べると近時の村長さんはこの件に関心がないように思えていたのですが、どっこい、切るに切れない複雑なもつれがあるようで、村としても簡単に坂井家から林野庁へ乗り換えられるものではないようであります。 25年7月17日 「官と官の対立」 ここ数回の投稿からして、林野庁という官と青森県および佐井村という官の間に、字牛滝川目130番1の所在場所を巡って意見の相違があることは隠しようのない事実と思われます。ことによると、このフェイスブックの指摘を受けて、「これまでうっかりしていました」として県や村が林野庁に謝罪・訂正するかもしれませんが、それでことが済むような話ではないでしょうし、もちろんそうなって欲しくありません。本来の力関係では劣勢なはずの県の林政課や佐井村が林野庁の見解に異を唱えるのはよほどのことのはずです。このようないびつなことが長年にわたって続けられていることも、当然ですが、異例中の異例でしょう。「犬が人を?んでもニュースにならないが、人が犬を噛めばニュースになる」と昔から言われてきています。こんな異例中の異例な出来事に何故にニュースバリューが認められず地元新聞が動こうとしないのか、私には不思議でなりません。最近は盛んにコンプライアンスが取り上げられ、官であってもその違反を無視することはできないはずです。林野庁と青森県・佐井村の字牛滝川目130番1の所在場所に関する見解の不一致は、いずれかの組織にコンプライアンス違反がないと生じないように思えてなりません。ただ、内容が専門的・局所的に過ぎて、外部の監視の目が入り込まないとすると、この種の案件はマスコミに頼らずに独自の手法で世に知らしめる他ないのかもしれません。ただし、県の林政課の対応はこのヒバ林事件の追及の仕方に大きなヒントを与えてくれており、私としてはその点については素直に感謝したいところです。 25年7月18日 「官と官の対立をあおってみる」 ヒバ林人質作戦が功を奏さないので、ここは、この官と官の対立をあおってみたいと思っています。私にはとても面白いと思える新たな展開なのですが、読者の方にどう映るかは分かりません。でも、何か打って出ないと局面の打開が出来そうにありませんので、やるしかないところです。 見方によっては、青森県林政課は私の主張を応援してくれていると言えます。それも公に。私の主張への賛同を公に表明している個人も組織もこれまで皆無に近い状態でしたので、その意味では画期的とも言えそうです。林政課にとっては迷惑な話かもしれませんが、私としてはその心意気に敬意を表したいところです。その裏を取材すればきっと面白い話がたくさん出てくる気がしますが、さすがにそこはニュースゲートのMCの仕事で私が入り込める世界ではないでしょう。肝心な点になると、「古い話で当時の資料がなく、何故不明確なのかはっきりしません」といった言葉で逃げられているのですが、県も村も公の組織として板挟みになりながらも一線を越えずに自治体としての最後のプライドを守っていると思え、非難をする気が起きません。いつかその時期が来たらぜひ協力してほしいとエールだけ送っておきます。 ヒバ林物語の本編を一応書き終えた去る4月に週刊誌数社にこのヒバ林をテーマにして投稿記事の記事化を検討頂けないかと依頼をしたことがあります。もちろん、どこからも返事はもらえていません。ただ、この「官対官の対決」というのはちょっとした新鮮さがあり、芸能ネタだけではなくたまには固い話も取り上げたいと思ってもらえるかもしれませんので、改めてコンタクトを検討してみようと考えています。あまり期待はせずに。 25年7月22日 「林野庁は孤立していた」 先月からの林地台帳を巡る官・官の諍いに加えて不動産登記を所管する青森地方法務局も林野庁との諍いに関わってきそうです。これまで知らなかったのですが、法的な理屈としては、法務局は職権で民有地の所在場所やその形状を特定し、不動産登記法が定める地図を作成できるようなのです。あまりに特殊で、私に経験のない事柄であり、断定はできませんが、本件のような所在地が宙に浮いてしまっている様な特殊なケース(それも2キロメートル以上離れている)では、本来は法務局が、恐らくは林野庁の請願を受けて、職権で130番1の所在場所を堂の上と決定し、その土地の形状を決め、公図(付属地図)とは似ても似つかない新たな地図を作成することが許されているようなのです。ちょうど、去る7月11日の投稿で示したリンク先の図面で県の林政課が黄色で示したような位置図を法務局が自主的にかつ公権的に確定できるということになります。しかし、そうだとすると、そうすることが許されているにもかかわらず、林野庁の云う最高裁判決が出てからでも既に36年以上がたっているのに、法務局に全くそうした動きが見られないのは何故なのかという疑問が湧いてきます。法務局も、「この地番に関する林野庁の主張は怪しい。判決もいい加減だ。足を引っ張るつもりはないが、こんなトラブルに巻き込まれるのは御免だ。」ということで一線を画しているとし考えられないように思われます。 民事裁判の手続きの一つに、特定の事柄につき特別の知見を有していると思われる官庁などに裁判所が調査嘱託という名で質問をし、回答を求める制度があります。土地台帳付属地図上の字牛滝川目130番1の所在場所が問題になったこの罠にはまった裁判においては、本来は当然にこの制度に従って法務局(むつ支局)の見解を正すべきだったと思われます。しかし、それがなされておらず、当然のように法務局は自らの見解を公にする機会を、幸運にも、逸したということになりそうです。 25年7月23日 「法務局の立場を推し量る」 普通に考えれば、現地牛滝の地理的特徴や土地台帳付属地図(公図)の正確性につき一番見識を有しているはずの青森地方法務局(むつ支局)としては、「(この公図は)全く信用できず、場所を特定するのに役立たない」と断言する裁判所に対しては、苦々しく思っていたことでしょう。しかし、同じ官庁仲間のやることに対して横槍を入れるわけにもいかず、「このことについては黙っておくが、これ以上こちらに迷惑をかけるなよ。」という辺りが法務局の偽らざる本心だったろうと思えます。林野庁から聞かれれば自身の見解を答えるにやぶさかではないが、他の役所が勝手に争っている民事裁判に自分の方から関わるのは二の足を踏まざるを得なかったということでありましょう。また、罠にはまった裁判で触れましたように、むつ支局は私に対する回答書簡においてこの130番1が公図においては牛滝から野平へ通じる牛滝川に沿った旧道に面していることを認めており、それは正に法務局が、最高裁判所の判断を否定し、130番が堂の上ではなく石山沢にあると判断していることを意味しているところであります。要は、公図は基本的に正しく、強いて言えば牛滝川の表示がこのヒバ林付近において省略されている、というだけのこととなります。 となると、字牛滝川目130番1がヒバ林から2キロ以上離れた堂の上にあると主張しているのは世の中で林野庁だけとなり、県も村も法務局も、「あの裁判は怪しく、信用できない。」と言っていることになり、多数決で言えば、林野庁の負けなのです。林野庁は孤立しているようなのです。私は、一連の裁判のトリックを見破りその裏付け資料を集めるのに数年を要しましたが、考えてみればこうした行政機関は裁判が進行する最中から「林野庁はえらいことをやってしまっているな。後で困り果てるだろうがそれは自業自得だな。」と高みの見物をしていたというところのようです。積極的に止めに入ることはせず、静観し、その後の林野庁からの協力要請には応じないという消極的対応に終始しているわけなのです。ここまで本件の実態・裏側が分かってくると、フェイスブックであれこれ力説するのがバカバカしくなってきます。「お主ら、少しは自分から声を上げたらどうなんだ!」、と叫びたくなります。
(以上)
|
|||
| アーカイブ 2026年 2025年 2024年 2023年 2021年 2020年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 |
||||