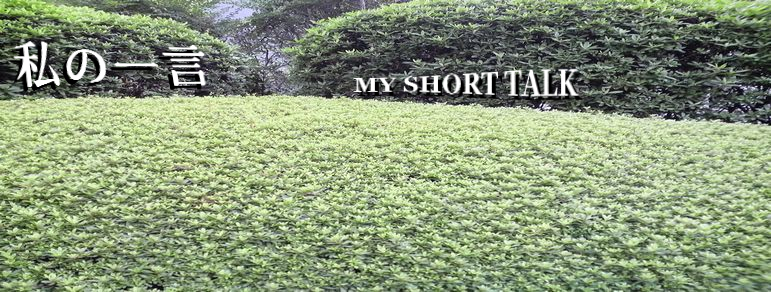 |
||||
| |
||||
| 公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の隠された謎に迫る) |
||||
127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密(自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん―その2 2025/1/29 94.第三者委員会という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
「明治・大正の官民境界査定図」なる図面の信ぴょう性 本ヒバ林にかかる裁判で林野庁から、字牛滝川目130番なる地番は堂の上にある約1万坪の実測面積を持つ土地であるとして、それを示す証拠として提出されたのが明治・大正時代の作成になる境界査定図なる書面である。結論から述べると、実際には、それらは昭和後期の本ヒバ林裁判提起前後に作成された書面である可能性が極めて高い代物である。ただ、そのような結論に至るまでには私もかなりの情報収集・分析が必要だったものであり、裁判所が審理期間内にそこにたどり着けなかったことについては無理のない面があると認めざるを得ないところがある。まさか林野庁がそんな破廉恥なことはすまい、との思い込みがあったとしてもなかなか責められない。 本ヒバ林裁判において裁判官に対して形式的ではあるが決定的な重みをもつものとして機能したと思われるのが添付の官民境界査定図なる書面である(資料13、「130番の境界査定図」)。そこには、牛滝川目130番の1と2との地番と所有者名として坂井源八が記載されており、それに隣接して127番なる地番の土地とその当時の所有者名である坂井峯吉氏の名が記載されている。しかし、まずもって根本的におかしいのは、堂の上にあった坂井家の土地は字牛滝川目ではなく、字細間に所在するという厳然たる事実である。この点を書面で端的に示す資料は持ち合わせていないのだが、昭和50年ごろに実施された国土調査の際に127番の土地の所有者(坂井峯吉氏の相続人)が係官を堂の上の現地に案内したところ、係官から「ここは字細間だから。(字牛滝川目127番の土地として)国土調査による地籍処理はできない。」と告げられたとのことである。勿論このことは峯吉氏の子孫からの伝聞であり、このことを記した書面まではないのだが、こと字界に関する限り誰もインチキは出来ないはずであるから、この点をじっくり調査すれば何れが正しいかは自ずから明白になるはずである。 但し、この峯吉氏の相続人の理解には落ちがあり、彼は、堂の上に所有する土地が字牛滝川目127番と信じていたようなのであるが、真実は、そうではなく、堂の上の峯吉氏が所有した土地は坂井家の同所の所有地がそうであったように未登記であったもので、字牛滝川目127番の土地はやはり付属地図が示すように牛滝川沿い(旧道沿い)にあり、本ヒバ林の近隣に位置しているのである(要するに字は細間ではなく牛滝川目)。地番と土地所在地の誤解がここでもみられるところである。三郎氏は坂井家の本家筋であり、江戸や明治の時代において度々分家筋に土地を分け与えていることから、このような似たような間違いが生じるわけである。また、堂の上の土地については所有者や村人が日常的に利用する機会が多く、登記だけの実態となってしまっていた旧道沿いの土地の方が失念されるようになっていたのが実体であろうと思われる。 過去の裁判における(投資家の)偽物との主張の持つ意味 この130番の査定図やその他の地番の境界査定図が昭和において作成された偽物であるとの指摘は、過去の裁判において多くの関係者が主張したことであり、それを裏付ける事実として、筆跡の相違、架空の職員名、使用された文字・数字が明治・大正において使用されていたものと合致しない等々の点が指摘されている。そうしたことは、連載7の資料9の新聞記事にもその一端が触れられているところである。しかし、過去の裁判においては、そうした相違ないし誤りは、それら図面があくまで昭和において林野庁により作成し直された複製であるということを根拠にして大目に見られてしまい、偽物の判断が避けられたようなのである。本来、複製であればなおのこと原物に忠実でなければならず、複製だからといった説明で済ませられるような間違いではないはずであること言うまでもあるまい。 しかし乍ら、逆に、明治や大正の時代に作成されたはずの多くの字牛滝川目の本ヒバ林近辺の地番の境界査定図が昭和の国土調査の結果得られた図面とそっくり一致するという不思議な事実があり、それらが偽物(少なくとも、元の図面の忠実な模写ではない)であることを強く示唆するところなのである。測量技術の違いを考慮すれば、現実にそのようなことが起こることは不可能なはずであり、裁判で国から提出された明治や大正に作成されたとされる境界査定図の複写なるものは、昭和50年前後になされた国土調査の結果に基づき、林野庁の希望に沿って、新たに作成されたもの(偽物)と強く疑われるところなのである。 坂井家が所有していた堂の上の土地は、未登記の土地なのであり、もし、それを明治や大正の時代に営林署が間違って字牛滝川目130番の土地と認識していたと言うのであれば、それは昭和の時代の18代源八が知らずに犯した間違いと同じ間違いをその当時の営林署が認識したうえでなしていたということになるが、さすがにそれは考えられないであろう。 長野の小林氏による偽物であることの証拠提示 こうした明治や大正時代の作成とされる一連の字牛滝川目の私有山林の境界査定図の怪しさについては、長野市在住の小林英勝氏が詳細に調査をし、林野庁にその結果を度々書面で報告している。その中の一つが字牛滝川目131番に関するもので非常に分かりやすい指摘をなしているため、過去の裁判で提出された種々の境界査定図の偽造の可能性を強く示す調査結果として本書に添付する(資料14―1「平成30年7月27日付小林氏書簡」)。小林氏の調査によると、昭和に実施された国土調査の結果(成果)として二つに分筆されることとなった土地(字牛滝川目131番1と2)が(資料14−2「131番1と2の登記情報」)、既に明治の境界査定図において2分割されていることが明白なのであり(資料14−3「明治の131番の境界査定図」林野庁により証拠提出されたもの)、少なくとも同土地にかかる境界査定は偽物であることは疑いようがないと思われるところなのである。なお、境界査定図と言われるものには、字の一定地域にある全ての私有地の国有地との境界を示すもの(全体図)と、そうした全体図を基に特定の地番につきその所有者に宛てて作成されたもの(個別図)があり、上記した資料13(130番の査定図)は坂井家に提示されたとされる個別図である。 このことはとても大事な点であるので、上記の小林氏の書簡内容をさらに裏付けるために、法務局むつ支局が保管する字牛滝川目131番の旧土地台帳付属地図(資料14−4)と現在の131番1と1の地図(資料14−5「国土調査に基づく131番の地籍図」を添付する。これらの資料を見ると、法務局が所管する新旧の登記簿や付属地図は昭和50年の国土調査に基づき131番がその1と2に分筆(登記自体は昭和55年)されるまでは単独地番として存在していたことが確認できる。ところが、林野庁が作成した明治の境界査定図では131番がその時点で既に2筆に分筆されたものとして記載がなされており又その所在場所も土地台帳付属地図が示す場所から国土調査の結果に従ったかのように大きく移動されていることが明らかなのであり、小林氏の指摘するように「あり得ないこと」が生じているところとなる。ただし、資料14−3の境界査定図の抜粋コピーは字牛滝川目をカバーした全体査定図面の一部であるため、かなり見づらく、私自身この査定図に記載された数字が131番であると確認しずらいが、この図面に対応する境界査定簿なる別の公式書面の記載と比べ合わせて理解すると完全な整合性があることが確認でき、添付の査定図面が131番の1と2を示すことに疑いを挟む余地はないところとなる(あまりに煩雑となるので、この査定簿の添付は控える)。このことは、査定図での131番の1と2の各形状が国土調査の結果により作成された地籍図が示す形状と瓜二つであることから、また、その測量ポイントも同一であることからも肯定されるところとなる。ちなみに、この131番は土地台帳付属地図上では石山沢を挟んで130番と向かい合ったところに位置していた土地である。 131番については、それが昭和の国土調査の結果により分筆されたものであるにもかかわらず、それより70年以上も前の明治の境界査定図において既に分筆がなされているという理解不能・説明不能な不可思議な事案であるために詳しく取り上げたのであるが、実は、他の土地に付いても、分筆問題はないようであるが、国土調査に基づく地籍図と明治の境界査定図が酷似し過ぎているという不可解さがある。一例として取り上げると、字牛滝川目132番であり、付属地図においては石山沢を挟んでヒバ林の対岸にある131番の隣に位置していたもので(資料3)、元の登記面積は99平米であったものだが、国土調査の結果に基づき4121平米に面積が拡張され(資料15−1「132番の登記簿」)、さらにその形状が地籍図として添付の資料15−2のごとく確認されている。驚くべきことに、明治における境界査定図において、この132番の境界・形状がものの見事に国土調査を先取りして正確無比に作成されているのである(資料15−3)。元の登記面積が国土調査により40倍以上にも拡張されたにもかかわらず、明治の境界査定図はそれらをものともせずに実相にたどり着いていたこととなる。しかも、図面に◯印で付された計測ポイントまで瓜二つなのである。小林氏によるとこの種の驚くべき類似性が多々見られるとのことであり、平坦地ではなく高低差のある山岳地帯におけるこのような計測数値・形状の一致は想像を絶するとのことである。 考えてみれば、裁判所は、片方では明治・大正の測量技術の稚拙さを理由にして土地台帳付属地図には信頼性が全くないと断定してその証拠価値を否定しながら、他方ではほぼ同時期に作成されたはずの境界査定図が昭和50年頃の測量技術と同一レベルであったものとして評価することを何の疑問も持たずに受け入れているのであり、あまりに不可解であろう。 そして、131番や132番にかかる境界査定図面が偽物(昭和50年ごろ以降の作図)であるとされると、字牛滝川目の境界査定図全体が偽物(同じく国土調査の結果に基づく昭和の作成)ということになってしまうのであり、その際には本ヒバ林を示すものとして裁判において林野庁から証拠提出された130番の境界査定図(個別図)も偽物とならざるを得ず、ことは極めて深刻である。 |
|||
| アーカイブ 2026年 2025年 2024年 2023年 2021年 2020年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 |
||||