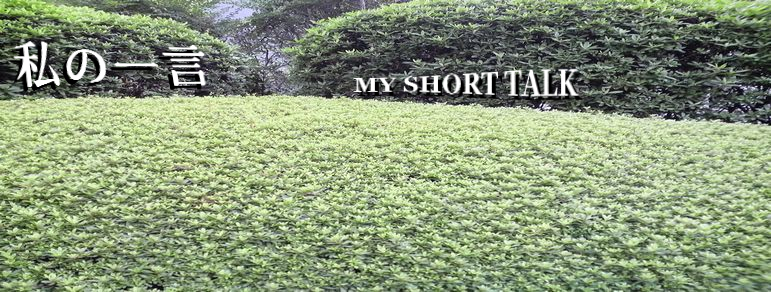 |
||||
| |
||||
| ヒバ林物語―第2部(佐井村の日本一のヒバの森)
|
||||
127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密 (自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん ―その2 2025/1/29 94.第三者委員会 という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が 宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ 家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない 広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
その11:係争が守った日本一のヒバの森 25年4月2日 「係争が守ったヒバの森」 裁判の裏事情については、刑事事件を含め、昨日までの投稿でほぼお伝えし切ったと思っています。詳しく話し出すときりがありませんので。もし、まだ、「役所がそんなことをするとは信じられない」と思われる方がおられたら、そうした方には「それなら、何故、このヒバ林だけが伐採を免れて今日に至っているのか」との疑問を持ってくださるようお願いしたいと思います。それを自問されると坂井家と営林署の紛争なしにはそのような奇跡は生じようがないことを理解されるものと思われます。生き残ったヒバ林自身がそれについての最後の証人となるわけです。私が、坂井家の人たちの話を聞く前から、この事件の判決は何かおかしいと感じ、又、林野庁の主張に疑念を持ったのも、この山のヒバだけが明治以降ほぼ無傷で残ってきているという不思議さだったところです。互いに権利を主張し合っていたことが、結果としてこの日本一のヒバ林を守ることとなったわけです。 ということで、この辺りで過去の経緯の説明を一旦終え、林野庁がこのヒバ林をその後どのようにとらえているかにつき、少しお話をしたいと思います。 昔の営林署は現在は森林管理署と名称を変えていますが、各森林管理署はその所管する林班につき5年に一度森林調査簿なるものを作成し、そこでの木々の生育状況を発表しています。私は、2年ほど前に東北森林管理局に行政文書の開示請求をし、平成5年度から平成30年度までの5年毎のこのヒバ林を含む2327林班の調査簿を入手しました。ほぼ似たようなものですので、その内の平成25年度分の調査簿の一部を添付いたします。リンク先は以下となります。 http://www.monobelaw.jp/material016.pdf またまた見にくくて恐縮ですが、左上に「林班2327」とあり、この書面がこのヒバ林にかかるものであることが分かります。注目して頂きたいのは、左寄りに「法指定等・・」の欄があり、そこに「係争地」と記載がなされていることです。実は、平成5年度以降の調査簿も、全て、同じように係争地との記載がなされています。ただ、平成30年度の調査簿ではそれが消去されています。この件は、非常に興味深く、林野庁のヒバ林に対する認識がどのようなものかを窺えるところがありますので、明日、さらに深掘りしたいと思います。 それから、昨日、このフェイスブックページをそのままネット記事にしてホームページでの掲載を開始しました。より多くの方に知って頂くための苦し紛れの作戦です。題名は「ヒバ林物語(係争が守った日本一のヒバの森)」となります。 25年4月3日 「森林調査簿での『係争地』の表記」 当然ですが、「係争地」という限り争う相手がいるはずであり、一体林野庁はどこの誰と平成30年ごろまで係争をしているつもりだったのか、との疑問が生じます。係争の相手として考えられるのは投資家と坂井家しかありませんが、私は坂井家の坂井三郎氏の代理人として令和5年4月に林野庁に対してヒバ林に関しての話し合いを求めましたが、林野庁からは「平成元年の最高裁判決で解決済み」として話し合いを拒否されております。それ以前においては、坂井家と林野庁間で表立った動きはなかったと聞いています。また、私は字牛滝川目130番1(現在の正式な地番名)の近時の所有者の動きも存じていますが、彼らが林野庁と平成25年当時に表立って争った形跡は見られません。もっとも、それ以前から130番1の名義人が過去の判決に不服でヒバ林問題の再検討を林野庁に働きかけていたという事実はありましたし、多分それは今もなくなってはいないと思います。しかし、そうした働きかけを以て係争地とのレッテルを張ったというのでは、役所の対応・認識としては何とも不可解な話というしかありません。私の面談要請に対する時のように「平成元年の最高裁判決で決着済み」とスパッと対処するのが役所らしいあるべき態度のはずです。そうではなく、もし誰かが不満を表明しさえすればそれでこのヒバ林が係争地になるというのであれば、一昨年の3月に私が正式に林野庁に交渉を求めた以上、そしてその後においてもネット等でこのヒバ林の問題を公開している以上、次の調査簿(令和10年)ではまた係争地に戻すのが筋となってしまいそうです。さて、どうなるのでしょうか。 ことのついでですので、私が林野庁に送った協議申入書と林野庁から届いた私との話し合いお断りの書簡をリンクしておきます。 http://www.monobelaw.jp/material90007.pdf 25年4月4日 「明治以来の係争」 私が森林調査簿の取得やその他のことで東北森林管理局と電話でやりとりをした際にも、担当の職員から、何度も、「この山は係争地ですから」と恐らく苦笑しながら言われたことを思い出します。少なくとも東北森林管理局や下北森林管理署ではこのヒバ林はどこまでいってもとても有名な「係争地」のようなのです。恐らく、日本中を捜してもこれほど長く係争地として扱われてきた林班は他にないと思われます。 実は、さらに興味を引くのは、下北森林管理署の現役職員が「係争は明治時代から続いています」と認めていることです。林野庁は、一連の裁判において、「過去において何人もこのヒバ林の権利を主張したものはなかった」と見えを切り、すなわち白を黒と言いくるめて、裁判官を安心させ大胆な判決を書かせていたのですが、さすがに組織の末端にまで完全にかつ長期にわたってかん口令を敷くことは不可能だったようです。徐々にそのほころびが出てきているということでしょう。この情報の入手経路についてはしばらく伏せさせていただきます。 既に1月24日の投稿記事その他で、地元の有力者である三村氏や工藤氏の書簡に触れ、昭和40年代半ばの裁判闘争の開始以前から18代源八と地元営林署との間でのこのヒバ林にかかる交渉がなされていた事実を明らかにしているところですが、それに加えて当事者の口からもそうした緊張関係が明治以来のものであることがはっきりとしてきたわけです。もっとも、普通に考えて、坂井家と営林署の係争は明治に遡る以外には始まりようがなく、昭和の裁判以前からもめ事があったとするならばその始まりは明治の廃藩置県・土地改革以外には見いだせないところです。ここまでくると、世間の常識的センスからすれば、係争の真相についてはもう完全に勝負あったと言っていいと思われるところでしょう。 想像でしかありませんが、下北森林管理署の職員がそうした話をする以上、同管理署にはそれを示すかなりの資料が今も残されていると思われます。その中には3月14日の投稿で掲載した明治27年の分筆にかかる字牛滝川目の完全な字図もあると思われますし、その分筆に営林署が与えたお墨付き示す内部文書も残されているはずです。役所の文書は例外的なもの以外はかなり短期間で廃棄することと規定されているようですが、良くも悪くも秘密的な内部文書はかえって長期間保存されているのではという気がしています。あくまで私の直感ですが。 25年4月7日 「払い下げの画策」 今となっては厄介者扱いになってしまっているこのヒバ林と何とか縁を切りたいと願う林野庁はその民間への払い下げを何度も画策したようです。最近では、2年ほど前にも同じような計画が進められていたところです。しかし、こうした企てはことごとく途中で頓挫しています。これにつき、私が罠にはまった裁判の連載の最終号で触れていますので、その一部を抜粋し、以下に掲載させて頂きます。
その12:下北半島・佐井村・牛滝 25年4月8日 「ヒバ美林プロジェクト」 ネット上の地元新聞等によると、近時、東北森林管理局は往年の青森ヒバの美林を取り戻すことを重要課題として、いろいろとプロジェクトを立ち上げておられるようです。そして、ヒバの森を肌で感じられる場所として、青森市から比較的近い津軽半島にある眺望山というヒバ林を盛んに広報されています。しかし、一方でこの牛滝のヒバ林のことは全く広報されていません。完全に無視なわけです。ネットで見ると、貴重なヒバの天然林とされる眺望山は44ヘクタール強の広さであり、本ヒバ林の56万坪(約170ヘクタール)とは比べ物になりません。恐らくヒバの数も数千本もあればいいところでしょうし、樹齢でも比較にならないはずです。 昭和10年の毎木調査による5万本が今も正しいのかどうかについては、はっきりとした答えは出せませんが、林野庁自身が、2327林班にはヒバが1万8千本ほどあると明らかにしています(この数値は、森林調査簿に記載されたヒバの材積数からの推定となります)。私はこの数字は意図的な過少申告と疑っていますが、その数値ですら、おそらく他のどこにもないほどのヒバの本数と思われるところです。しかし、それでも一切この宝の山は一般の目には触れないようにされているわけです。林野庁が如何にこのヒバ林を恐れているかが知られるところです。また、このヒバ林に何度も入ったことのある三郎氏によると、ヒバ林にはヒバ以外の樹種はほとんどないのに、何故か、森林調査簿にはブナやナラも多くあるように記載があるのが不思議で仕方がないとのことです。そして、「一体この林班はどこの山のことを言っているのだろう。」とまでつぶやかれています。 本数についての疑問は一旦置くとしても、森林調査簿によりますと、ヒバの平均樹齢は180年とされています。平成30年から180年前というと明治維新のほんの20数年前となります。それはあり得ないだろうと思います。昭和10年の毎木調査で、樹齢300年から400年とされていたヒバがそんなに若返るとは思えません。いずれにしろ、何時かこのヒバ林が世に出された際にはヒバの樹齢がどのようなものかはっきりするはずです。そうなのです、このヒバ林は時限爆弾のようなものでいつか必ずその実態が世間の目に触れることになります。問題はそれが何時になるかです。 25年4月9日 「ヒバ林を避ける実情調査」 以前にお話ししましたように、ネットで探してもこのヒバ林にかかる記述はごく限られた裁判に関するものか、私の記述及び朝日新聞の記事しかありません。そのような状態の中で、下北半島の自然林に的を絞って学者や環境問題の専門家(後に、「日本の天然林を救う全国連絡会議」なる組織となる)が実情調査をなしたとする記事がありました。記事が林野行政に対して批判的な論調であったので興味を覚え、同連絡会議や調査に参加された方に連絡をしたことがあります。その時に発信したファックスがありますので、ネット記事と共に参考に添付します。リンク先は以下となります。 http://www.monobelaw.jp/material90008.pdf この記事が掲載されたのは平成28年頃のことと思われ、既に関係者も第一線を退いたり、転職されたりと移り変わりが激しく、このファックスへの回答は得られませんでした。しかし、記事の内容からすると、調査団の方々が下北のそれも恐山の近くのヒバの状況を観察され、国有林の惨憺たる状況を目の当たりにして憤りを感じられていることからして、青森森林管理署(事務所)は調査団に対して石山沢の立派なヒバ林のことは何も話されなかったようなのです。 著名人が集うこのような民間の有志団体による国有林の実情調査に協力する以上は、東北森林管理局としては最低限のサポートをすべき立場であったでしょうに、直ぐ目と鼻の先にある佐井村の日本一のヒバ林の存在を隠し通しており、何ということかと私まで義憤を感じてしまいます。これでは、第2次大戦における大本営発表と何ら変わりがありません。ことのレベルは違うとはいえ、いまだに同じような言論統制がまかり通っているのは、何とも情けないところです。ましてや、このこと(立派なヒバ林の存在)は林野庁にとっては都合の悪いことかもしれませんが、本来的には青森県民や国民にとって歓迎すべきことなのですから。私がこの事件に深くかかわる理由はまさにその点にあります。 よく大手企業で不正な社内処理が何十年となく続いたといったことがニュースになりますが、分かっていても先輩の関わった不正を自分の手で表面化させるのは皆が二の足を踏むのでしょう。それでいつの間にか40年というわけです。誰かがどこかで止めないと。困ったものです。 25年4月10日 「豪商・坂井家」 私は弁護士として佐井村の坂井三郎氏から依頼を受けてこのヒバ林の真相を解明し、その上で然るべき対応をなすことを期待されている立場にあるのですが、その坂井家につき書かれた今から30年ほど前の新聞記事がありますので、本来的にはこのヒバ林物語の主人公である坂井家の紹介に代えて下記にリンクします。現在の下北半島から受ける印象からは想像しにくいのですが、江戸時代においてこの地が日本海交易の中心の一つとして大変栄えていたことがよく知られます。そして、その筆頭格に坂井家があったところなのです。 http://www.monobelaw.jp/material002.pdf この記事で扱われている古文書は、その後に整理され、現在は東京都中央図書館に保管されているはずです。 また、江戸時代に坂井家が山守頭として佐井村一帯の山林を管理していたことを示す南部藩に納めた古文書の表紙とその中の本ヒバ林を示すページを下記にリンクします。少し見にくいのですが、そこに牛滝石山と書かれているのが見えると思います。そこが石山沢のヒバ林です。そして、その当時既に坂井家が南部藩からこのヒバ林の下賜を受けていたので、ヒバ山の状況を藩に報告する義務がないことから、このヒバ林の部分だけは一見するとはげ山のようにヒバの絵が書かれていないというわけなのです。なお、江戸後期に東北地方を襲った飢饉に際して、当時の源八が坂井家の蔵に保管されていた米を村人に分け与えて飢餓を防いだことから、そのご褒美としてこのヒバ林が坂井家に下賜されたと聞いています。また、その際、同源八に限り「源右衛門」を名乗ることが許されたということです。私が映画「飢餓海峡」に何とも言えない親近感を感じるのはひょっとするとそうした歴史の一幕のことが私の脳裏に残っていたからなのかもしれません。 http://www.monobelaw.jp/material001.pdf 25年4月11日 「政治力があだとなる」 このように、明治政府が本格的に権勢を振るうようになるまで坂井家はこの地に根を張る隆々たる商家・豪商であり同時に山主だったところです。維新に際しても、戊辰戦争で函館に向かっていた西郷隆盛に坂井家から資金提供をなしたとのことであり、また、勝海舟とも当時の17代源八は交流があったとの話です。ここで少し脱線しますと、勝海舟は自身か父が勝家に養子に行ったもので、父方か母方の元の姓は物部であったらしく、海舟はそれを誇りに思い常に小さな物部守屋の像を身に着けていたとの話です。当然ながら、私としてはそこに親近感を感じてしまうわけです。 しかし、明治期におけるこのような特異な政治力の保持が、このヒバ林に関する限り、かえって坂井家にあだになったと思われます。南部藩から下賜された170町歩に及ぶ広大なヒバ林を維新当初にたった1反6畝2分の広さで地券を受け、すでに記述しましたように明治27年には堂々とすべてをオープンな形で完全に10分の一の縮尺で経済的価値の高いヒバ林の登記をするなどといったことは、それが営林署の了解を得たうえでのこととはいってもあくまで口頭でのことでしょうから、よほど自分の政治力に自信がないとできない芸当であったはずです。そのような並外れた政治力を有していたことが結果としてはあだになったと云えるでしょう。地租を抑えたかったのでしょうが、せめて、その時に営林署も同意した境界線に沿って実面積での分筆登記をしておりさえすれば、今に至る昭和後期からの不可解な争いは生じなかったはずなのです。 25年4月14日 「佐井村の日本一のヒバ林」 日本一のヒバ林の裏話を終える日が来ました。この時期に触れるのは遅すぎるかもしれませんが、佐井村につき少しお話をしたいと思います。佐井村のホームページを見ていただいた方がいいのかも知れませんが、本州最北のこの地に縄文時代の遺跡が数多く出土しているとのことであり、今では想像しにくいのですが、古から土着の文化を有していたようであります。そして、既にお知らせしましたように江戸時代は北前船で交易の中心となっており、決して辺境の地ではなかったところです。現在佐井村は、「日本で最も美しい村」連合に加盟し、村の木は「ヒバ」と定められています。私は、村の自慢として、一日も早くこの宇志多岐小川(石山沢の名称より有難い感じがします)の日本一のヒバ林を取り上げて欲しいと思っています。それが誰の所有かなどということは関係のないところです。 このヒバ林をGoogle Earthで見ると、ヒバ林を含めて山全体が緑に覆われてしまっており、残念ながらヒバを特徴づけるだけのものを見いだせません。ドローンと最新のAIソフトを使うと90パーセント以上の確率で樹種や樹高果ては幹の太さまで判明するようなのですが、いかんせん費用が高額で手が出せません。そういうことで、本州最北のしかも県中心部から最も遠い最果ての地といえる佐井村・牛滝のヒバ林は今日も誰にも知られずにいるわけです。 明治維新の土地改革から数えて160年近くにわたり下北の宝が隠され続けているというのは、あまりにヒバが可哀そうに思えます。私がその無念さを唄にしました。一般にヒバの生木としての寿命は400年から500年とされているようであり、かなりその時期が近づきつつあるのではと心配されます。 「ヒバ林の唄」 ヒバよ オレの声が聞こえるか ヒバよ、お前のことは知っている 幾百年の風雪に、耐えて育ったヒバ林よ 晴れて天下に知られるその日まで あと少しの辛抱だ オレがついている
完
|
|||
| アーカイブ 2026年 2025年 2024年 2023年 2021年 2020年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 |
||||