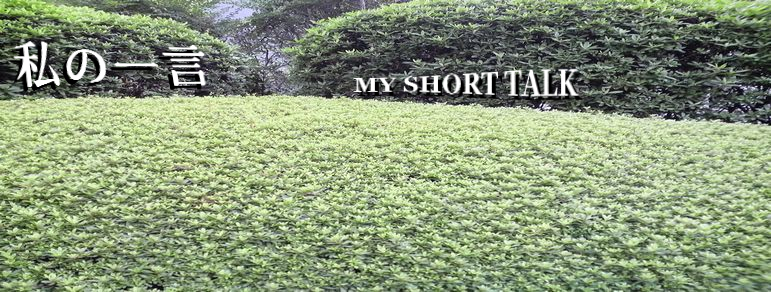 |
||||
| |
||||
| ヒバ林物語−第2部(佐井村の日本一のヒバの森) |
||||
127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密 (自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん ―その2 2025/1/29 94.第三者委員会 という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が 宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ 家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない 広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
その1:昭和の疑惑の移転登記と明治の不可解な分筆登記 25年1月6日 「存在を否定された山」 存在を否定されている山というと大げさかもしれませんが、下北半島の西岸の津軽海峡・平館海峡に面する佐井村の牛滝にある天下一のヒバ林は正にその状態です。何故、そんなことが起きたのか、そのことをお話ししたいのですが、どこからどのように話せばいいのか、正月休みの間ずっと悩みました。昨夏の私のネット記事はことの順番を守って説明・解説していますが、それでは一般の方にとってはつまらないでしょう。私にその力量があるかどうかわかりませんが、少し小説風に話しを前後させながら、この不思議なヒバ林を解き明かしたいと思います。ということで、明日、スタートします。 25年1月7日 「争いの原因」 天下一のヒバ山と言っていい牛滝川の上流の石山沢の西岸に広がるヒバ林は明治維新を境にして、そのどこまでが南部藩から下賜を受けた坂井家の所有なのかにつきはっきりした資料がないことから(公図は意図的に100分の1程度に縮小されていた)、国有林との境が不明確な状態となってしまっていました。それがため、宝の持ち腐れではあるのですが、このヒバ林は今日に至るまで長年にわたり伐採を免れてきたこととなります。本来、牛滝の住人である坂井源右衛門が江戸時代に南部藩からご褒美として下賜を受けた山林なのですが、土地台帳制度や登記制度の整備の過程で過少申告がなされ、それがその後に悪影響を与えたところです。そのような官民の諍いは全国的に生じてお決して珍しいものではないのですが、このヒバ林の場合は、それが単なる面積の問題ではなく、その所在場所の問題にすり替えらてしまっており、極めて異例なケースなのですが、それについてはおいおいご説明致します。そうした背景の下で、昭和35年に不可解な土地所有権移転登記がなされ、そのことが原因となって昭和40年中ごろからその後30年近くに渡る裁判闘争が繰り広げられることとなりました。不可解な移転登記の元となる売買の対象となった土地は、同じ牛滝の堂の上と呼ばれるところにあった18代坂井源八所有の別の土地であり、買手は地元の住人であった中西幸一氏で、代金は12万円であったようです。 この堂の上という所は、牛滝集落にも近く、比較的平坦な山であることから、柴刈りや植栽に適しており、坂井家もよく出入りしていた山ですが、中西氏からその海側の半分ほど(約5千坪)が欲しいと頼まれて、分筆の上でこれに応じることとしたものです。 国土地理院の地図に、本ヒバ林と堂の上の土地の位置関係を示すと、別紙のようになり、リンク先は以下となります。そこで字牛滝川目130番という地番で示された場所が旧土地台帳付属地図で記載された坂井家が南部藩から下賜を受けたヒバ林の一部を表すこととなります。本来は56万坪余りあるヒバ林全体を登記すべきはずでありますが、当時はこのように大幅に小さく登記をなすことが特に山林においてはごく普通のことであったところです。租税の負担を恐れてのこととなります。堂の上の土地は、そのヒバ林から2キロメートル以上も北西に離れています。 http://www.monobelaw.jp/appendix001a3.pdf 実は、坂井家が従前から所有していた堂の上の土地は未登記の土地であり、しかも字牛滝川目ではなく字細間という場所に位置しており、本来はその移転登記なる手続きは出来ないはずであったのですが、ここで間違いが生じてしまいました。源八から移転登記の依頼を受けた地元の測量士の飛内源一氏が、堂の上の土地を示すような登記が見つからないことから地元営林署(恐らくは牛滝担当部署)の職員に相談したところ「坂井さんの土地なら字牛滝川目に1万坪ほどの広い土地(130番)があるよ」と聞かされ、同測量士はそれが堂の上の土地を示す登記と勘違いをしてしまった次第です。最終的には最高裁判所にまで行く全ての間違いはこのことから始まったところです。 25年1月8日 「不可解な二度の分筆」 売り手も買い手も堂の上の土地を半分に分筆して売買したつもりだったわけですが、その登記手続きについては全く無関心であったため、このような大きな間違いがその後数年間、誰にも(後に触れますように営林署関係者を除き)知られずに推移したところです。 話がややこしくなりますが、ここでどうしても明治27年に17代源八によってなされた字牛滝川目130の地番のその1と2への分筆に触れなければなりません。元々は、この地番はさらに小さい面積で明治の初めにその登記がなされていたものですが、源八がヒバ林を測量の上で二つに分筆し、ただし、1:2ほどの割合で土地を直線的に分けたものであります。しかも、源八は、本来の測量数値のきっかり10分の1の数値で登記(分筆)をなし、実際の面積を示す測量図は別途に村役場に提出するという何とも不可解な処理を行っていました。その詳細については後に触れることとなりますが、ともかく、18代源八は既に明治の時代にこの登記地番が1:2の割合で二筆に分筆されていることを知らずに「海側の半分が欲しい」との買い手の意向に従い、単純にそれぞれを2分し、具体的には、新たに附番された130番の3と4を買い手の中西氏名義に移転登記してしまったものであります。しかし、これらの二つの地番は隣接しておらず、別紙のように飛び地になっているのですが、売買当事者は一切そうした書面上の流れにお構いなしであったところです。この別紙のリンク先は以下のとおりなります。 http://www.monobelaw.jp/appendix003.pdf 話が複雑になってしまい申し訳がないのですが、本ヒバ林を示すはずの字牛滝川目130番という地番がかかる2度の不可解な分筆を経たものであることを理解して頂かないとその後の話しに結びつかないところです。 すなわち、 1.明治27年の分筆は、意図的に実測図の10分の1で登記申請がされ、それとは別途に実測図が村役場に提出され、 2.昭和35年の分筆は、本来分筆対象とすべきでないこの石山沢のヒバ林にかかる土地登記を結果として4分し、130番の1〜4と分筆した。 以上がこの裁判ミステリーと言ってもいい事件の基礎事実となります。 25年1月9日 「堂の上の土地のその後」 ややこしすぎて、読む気が起こらないことを心配しています。その上で、このまま話を続けることとします。 昨日お話ししましたように、売り手も買い手も問題のヒバ林とは何の関係もない、場所的にも2キロ以上離れた、堂の上という高台の土地を売買したわけですが、その後昭和39年に18代源八が亡くなり、残された堂の上の土地(登記簿上は字牛滝川目130番の1と2)がその翌年に息子の弘氏により札幌の横井氏に売却されました。これにより、堂の上の土地と本来ヒバ林を意味する字牛滝川目130番の1〜4の登記は全て坂井家から離れることとなってしまいました。そして、その間、この実体と登記の不可解な関係(齟齬)につき知っていたのは一部の営林署の関係者しかいなかったということになるわけです。ただ、その後しばらくして、この売買実態と登記のずれの問題が表面化することとなります。長い紛争の始まりとなります。 25年1月10日 「営林署の思惑」 実は、この案件を扱い始めた頃においては、私は、営林署も字牛滝川目130番という地番が堂の上の1万坪ほどの土地を意味すると思っていたのでは、と推測していました。まさか、意図的に間違った登記をさせたとまでは想像できなかったのです。ところが、いろいろ調査をすればするほど、それがあり得ない、「営林署は意図的に間違った登記をさせた」と確信するに至っています。その根拠の一つは、正にその当時、18代源八は地元青森県の有力者を通じて県や国にこの広大なヒバ林の権利問題の解決を依頼していたという事実を知ったことでした。それを示す2通の書簡が見つかり、それらから石山沢のヒバ林に関して当時の青森県知事までを巻き込んだ話し合いがなされたいたことがはっきりしたからなのです。うち1通は、当時の青森県会議員で後に県会議長になった三村泰右氏から源八に宛てたもので「県及び国に対して機会ある度に交渉を致しておきますから私の力の及ぶ限りの政治力にて解決いたします」と記されています。このような状況で、地元営林署が石山沢沿いの坂井家にかかるヒバ林の問題を知らないはずがなく、その争いの中心にある字牛滝川目130番の地番を源八が第3者に譲るわけもないわけであります。勿論、その当時の交渉において営林署サイドから「字牛滝川目130番の土地は、石山沢沿いではなく、2キロほど離れた堂の上にあります」といった反論がなされた形跡は皆無であります。 では、何故営林署はそんな詐欺まがいのことに手を染めたのか、それについては明日以降にお話しします。 25年1月14日 「山林登記の実態」 私も田舎に小さな山を持っています。父が亡くなった際、親戚の年配者の方に現地を案内され、「この木が境界だ」「このあぜ道が境界だ」といったことを聞かされました。山の境界というのは現実にはそうした手法でしか対応し得なかったわけです。ということは畑と違い普段使用しない山の境界というのは、関係者がそれをよく知っているという間柄でないと、わけの分らないことになる運命にあります。明治の代になり、それ迄の支配体制が代わり、いわゆる中央集権になると、それ迄の村と村人との関係にも根本的な差が生じます。村は、村人の集まりであると同時に、中央政治の出先機関としての立場を兼ねることになり、そこに軋轢の芽が生じました。全国各地で、民有地とその周りの国有地の間で境界紛争が生じたわけです。この佐井村のヒバ林もその一つで、江戸時代においては石山沢の西岸の峰に至る広大な山全体が坂井家のものと村からも認められていたのですが、その後において時が経つにつれ地券の交付やその後の土地台帳への登録面積が実態よりはるかに少ないことが問題となったわけです。皆が当然のように村の了解を得て公式に行っていた過少申告が大きな弱点となって降りかかってきたわけです。本ヒバ林事件もこうした全国的な紛争の中の一つに過ぎないのですが、それが単なる面積の問題ではなく、場所の問題にすり替えられたという意味では極めてまれな事件となっています。 25年1月15日 「過少申告の報い」 坂井家は江戸時代から名の通った地元の名家であり、ヒバ林の地券や土地台帳への登録に関して役所から便宜を受けることに疑問はなかったと思われます。それが当時の一般的慣行でもあったところです。しかし、登録面積の少なさが、時がたつにつれ、両者の妥協を難しくしていったと思われます。また改めて触れますが、明治27年に17代源八がこのヒバ林を1:2で分筆したのは、そのどちらかを国に譲って手打ちをする算段をしていたと思われます。売れる当てもなく費用をかけて山林を分筆をすることは考えられず、また、その様な紛争の対象土地を購入する人もいなかったはずですから。でも、そうした段取りもとん挫してしまい、終戦を迎え、先日お知らせしましたように18代源八は何とか政治的解決をと願ったようですが、それもまとまらない状況であったことが知られます。 坂井家も営林署もにっちもさっちもいかない袋小路に入り込んでいたわけです。そんな時に、「ひょっとしたら今後の坂井家との交渉に有利に使えるのでは」と営林署に思わせたのが堂の上の土地取引にかかる130番の移転登記となります。「決め手になるとは思わないが、交渉をより有利に運ぶ材料になるのでは」といった元は軽い気持ちからの発想ではなかったかと想像されます。あくまで私の推測と批判されるかもしれませんが、それ以外にはあり得ないことをこれから少しづつお話していくこととなります。 25年1月16日 「国有林」 国有地は、一部の例外を除いて、公図(土地台帳付属地図)には「国有地・官有地」との記載はありません。ということは、過少申告に基づいて山林の位置を示す公図が作成されると、その過少申告された部分の山林は私有地とは分からなくなり、事実上は国有地となってしまうリスクがあります。村役場や中央官庁の地元担当者と顔見知りの時はそれでも大丈夫だったのしょうが、担当者が代わり、新しい責任者が東京から派遣されてくると、当然、本当の境界ははどこなのか、ともめることになるわけです。会社の2重帳簿の問題と似ています。資産隠しをしていたら本当にその資産を失うリスクがあるということになります。 実は、官民査定という制度があり、明治から大正にかけて、建前上に過ぎないかもしれませんが、私有林と国有林の境界を定める手続き制度がありました。これが正規に完全になされていれば、この種の問題は防げたかもしれませんが、少なくともこのヒバ林はそれがなされていなかったのは間違いないと思われます。後に、林野庁はこのヒバ林の官民査定の書面を裁判で証拠として提出してくるのですが、それが本物で昔からあったのなら、このような明治以来の坂井家との長い緊張関係や昭和後期の裁判を交えた投資家との紛争は起こらなかったはずと思われるところであります。 いずれにしろ、堂の上の土地と字牛滝川目130番の地番を結び付けておくことが後で何かの役に立つと地元営林署は判断したものと思われます。本来は愚策に過ぎないものだったのですが、その後その無理筋が通ってしまい、とんでもない間違い判決を生むのですが、それはまた先でお話しします。 25年1月17日 「明治27年の分筆の目的」 実は、そうした営林署(最終的には林野庁)とのトラブルを解決するために、17代源八は、明治27年に広大なヒバ林を1:2の面積比でほぼ一直線に二筆に分けたようなのです。多分、小さい方の130番1を国有地として差し出すつもりだったと思われます。というのは、大きな130番2を差し出すと、坂井家のヒバ林が四方八方を国有地に囲まれる形となり、気分が悪いでしょうし、面積も大幅に減ります。1を差し出せば、境界の半分は石山沢となるので、もめごとは少なくなります。源八としては、ヒバ林の3分の1も差し出すのだから、国も不満はないだろうと考えたものと思われ、また、地元の営林署からそれでまとまるような感触を得ていたのでしょう。「既に話はまとまった」と思っていなければ、多額の費用をかけて測量・分筆はしなかったはずと思われるからです。しかし、このヒバ林に経済的価値があり過ぎたのがあだになり、最終的にはこの交渉はその後頓挫したようです。ただし、土地台帳への登録数字は実際の測量値の10分の1の長さで申請し、本当の数値(図面)を村役場にだけ提出するというのんきな対応をしていますが、おそらく事前に営林署から「それでいい」との非公式な了解を得ていたのだろうと思われます。 ここで、この明治の分筆の結果がどのように土地台帳付属地図(公図)に反映されたかを見ていただくために、字牛滝川目の公図を添付します。リンク先は下記のとおりです。 http://www.monobelaw.jp/material003.pdf とても見にくいのですが、中ほどにある大きな区画の土地が現在の公図上の130番となります。実際のヒバ林の極一部なのですが、それでもその他の土地に比べると際立って大きくなっていることがお分かりいただけると思います。源八としては、思い切って大きな面積で登録し直したつもりだったと思われます。 同様に、土地台帳登録のために源八が作成・提出した分筆届とその図面を添付します。リンク先は下記のとおりです。 http://www.monobelaw.jp/material005.pdf 25年1月20日分 「昭和10年の毎木調査」 手元に昭和10年に岩手県の岩泉町森林組合がこのヒバ林の毎木調査をして作成した一覧表があります。勿論写しで、とても見にくいのですが、リンク先を下記に記しますので、見ていただきたいと思います。 http://www.monobelaw.jp/material006.pdf その当時坂井家の戸主は既に18代源八に移っていましたが、婿養子であったこともあり実際はやり手と言われた妻の「りそ」さんが坂井家を差配していたようで、彼女が森林組合に調査依頼をしたもののようです。 調査書の重要な点に触れますと、対象山林の地番が字牛滝川目130番4と記されています。その当時は、まだ再分割はされておらず、130番は1と2の枝番しかなかったのですから、この記載が間違いであることは確かなのですが、登記簿上のヒバ林全体の3分の2を占める130番の2の書き間違いかと思われるところがあります。と言いますのは、対象面積が(実測値として)120町と記されており、その2だけの推定実面積とほぼ合致するからなのです。ことによると、その当時、りそさんは依然として130番の1を国に差し出すことでもめ事に終止符を打とうとし、そのために、坂井家に残されることとなる130番の2のヒバの数を知りたかった可能性があるように思われます。そして、ヒバは総数で約5万本と数えられ、その多くが樹齢300年から400年とされています。江戸時代に南部藩が植樹したものがそのまま残されたのですから、当時ですら既にこれほどすごいヒバ林になっていたわけです。普通に考えると、このヒバの質と量はとんでもない経済価値を意味したはずです。 明治27年の分筆と同じく、かなりの費用のかかるこの毎木調査が何の目的でされたのかははっきりしないのですが、やはり国との争いに絡んでその解決のためにしたとしか考えられないところと思われます。毎木調査は実際に山に人が入ってカウントしたわけで、その際には登記簿の面積ではなく、坂井家のヒバ林としてりそさんや村人の認識に従い石山沢の西岸一帯をその対象にしたはずです。この点については、後日、改めて説明したいと思います。勿論、そうした調査につき、当時の営林署がクレームをつけたといった記録は全くないようです。 それと、これは指摘するまでもないでしょうが、この調査書により字牛滝川目130番という土地が、堂の上の山林ではなく、石山沢のヒバ林を意味することが明らかにされているところです。堂の上の土地は1万坪ほどの大きさしかないうえに当時ヒバは全くなかった山ですから、森林組合はりそさんから頼まれて民有地である石山沢のヒバ林の毎木調査をしたことに疑いを入れる余地はないこととなります。今日は、少し、長くなりました。 25年1月21日 「奇跡的に残されたヒバ林」 前に触れましたように、ヒバは成長が遅い代わりに例外なく高密度木材となります。ヒノキが「木曽ヒノキ」と一般のヒノキでは品質・価格に大きた差があるのとは違い、ヒバは年代物でありさえすれば全て超の付く高級木材になるというわけなのです。そうしたことから、昭和30年代においては林野庁の配下にある地元の営林署としてもおいそれとは石山沢のヒバ林につき坂井家と手打ちをできないような大事な代物になっていたものと思われます。また、戦前戦後と木材需要が旺盛で、言ってみれば、青森県下のヒバは軒並み切りまくられた結果、この牛滝のヒバ林が最後に残された聖地のような山になってしまっていたわけです。ちなみに、以前お伝えしました森林鉄道が青森県の津軽半島と下北半島に張り巡らされ、この木材需要に応じたわけです。その意味では、明治以来の坂井家と営林署の争い、そして、その後の130番の地番の罠を通じた主に林野庁と投資家間の裁判沙汰という緊張関係の継続が、事実上は、このヒバ林を伐採から守り抜き、今に残したと言えそうなのです。 以上 |
|||
| アーカイブ 2026年 2025年 2024年 2023年 2021年 2020年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 |
||||