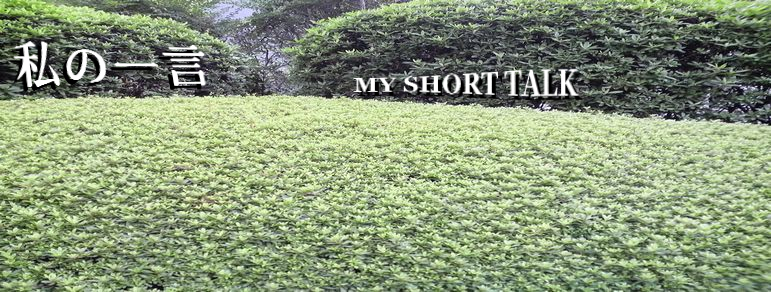 |
||||
| |
||||
| ヒバ林物語―第2部(佐井村の日本一のヒバの森)
|
||||
127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密 (自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん ―その2 2025/1/29 94.第三者委員会 という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が 宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ 家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない 広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
その7:林班制度 25年3月13日 「林班制度について」 今日は、林野庁の反論の根拠として主張された林班というものにつきお話ししてみたいと思います。林班という制度のことは私もこの事件に関わって初めて知ったのですが、要は営林署が現地の山林の管理のために便宜的に管轄地を地形に沿って適当な広さで分け、それに番号を付したものにすぎません。裁判において、林野庁はこのヒバ林の場所はそうした意味で言えば127林班にあたると主張したわけです。その後、附番の仕方に変更があり、現在は2327林班と称されています。 この林班はあくまで林野庁の内部処理上のものであり、また、必ずしも対象地を国有林に限定しているものでもありません。そういうものですから、所有権の立証に関してはさほど法的な意味合いのあるものではないのですが、過去の森林管理の実績を強調して間接的に国有林であることを立証するためには役立つものとなり得ます。しかし、本ヒバ林に関してはそうした事実上の立証価値すらありません。何故かといえば、明治以来の坂井家との緊張関係から互いにこのヒバ林ではヒバの伐採をせずに来てしまい、過去の実績というものがないからなのです。127林班というものが形式上以前からあったとしてもそれはその名前があっただけなのです。私が、本件の一番の証人はこのヒバ林そのものであり、手つかずに今日まで残されていることがこのヒバ林が明治以来どのような立場にあったかを雄弁に物語っている、と指摘する所以であります。大掛かりな山火事でもない限り、この証拠は誰も壊したり改ざんしたりできない点が強みとなります。 言うなれば127林班には山林管理の単位として実際に機能した実績がなく、紙だけの存在と言っていいようなのです。12月9日の投稿で触れましたように牛滝森林鉄道が昭和24年に牛滝港からこのヒバ林の袂(上牛滝橋)まで設置されたのですが、このヒバ林からは一本のヒバも切らずに昭和37年に撤去されてしまっているという事実がそのことを雄弁に物語っているところです。このこと一つを取っても、127林班というのは形だけでやる気が皆無なのです。もちろん、過去の裁判において、林野庁は、この林班においては過去に何らの紛争もなく林班として管理してきたと言い切り、それがそのまま裁判所に認められたところです。 その8:全てを語る牛滝の字界図 25年3月14日 「字牛滝川目の字図」 さて、以前の投稿で少し触れました佐井村の牛滝集落を中心にした字界図、というより17代源八が佐井村役場に提出したヒバ林の実際の分筆図面に基づく字牛滝川目の字図を、ここでお示ししたいと思います。リンク先は下記となります。実際の図面はもっと大きかったようですが、その内の中心部に限ってカラーコピーされたものしか私は入手し得ていないところです。ある意味でこの図面を正しく理解して、初めて、私は完全に坂井家が歴史的にヒバ林の権利を有していたと確信した次第です。私にとってはそれほど重要な資料となります。 http://www.monobelaw.jp/material004.pdf この図面については、1月17日の投稿で、明治27年に130番がその1と2に分筆された経緯を述べた際に少し触れているのですが、リンク先の掲載は省略していました。フェイスブックを見られている方に、もう少し後にこの図面をお見せし、私がそうであったように、いろいろな調査分析をしてほぼ坂井三郎氏の云っていることが正しいと信じられるようになった時に、この図面の意味・価値を正しく理解していただき何が本当かにつき確信を得てもらいたい、という気持ちがあったからです。実は、この図面は調査を始めて2年ぐらいたったころに坂井氏から取得していたのですが、その当時は「役には立ちそうなのだが、大雑把で、決定打にはならないな」と思っていました。そんな状態でまる1年半ほどが経った頃に、突然、この図面と17代源八が登記所(当時の税務署)に提出した分筆申立の添付図面(1月17日の投稿でリンク先を記していますが、再度下記に記します)が全く同一の中身であることに気がつきました。同一というのは、同じ数字が書かれているが、単位が分筆登記申請の添付書面では10分の1に縮小されているに過ぎないということになります。このことに気づいた際の私の驚きとともに、日を改めて詳しく説明を致します。 http://www.monobelaw.jp/material005h2.pdf 25年3月17日 「完璧な相似性」 具体的に説明しますと、両図面に書かれている数値が正確に1:10で対応しており、実質的には全く同一の数字が記載されているという事実です。少し見にくいかもしれませんが、字図の牛滝川の「牛」の字の少し上からまっすぐに右に伸びる線の下に、2170歩(ただし、漢数字)、と記載があるのが読めると思います。実は、この数値が分筆登記の添付図面では、217、という数値に置き換えられています。よく見ると、他の数字も字図では10倍を意味するように0が加えられています。逆に言えば、登記書面ではゼロを消して長さを10分の1に縮小していることとなります。17代源八は、村役場には実測数値そのままでの分筆図面を提出し、登記役場にはわざわざそれを10分の1の長さに修正したものを提出していたわけです。それも村役場に提出した正しい図面ではそれらの数値の単位が「歩」であることを明記しながら、分筆申請用図面ではその単位を伏せているところです。1歩はほぼ1間に相当するようですが、歩数で距離を測るような際にはこの「歩」が距離の単位として用いられていたようです。大雑把に言えば、ヒバ林は、南北の長さが4キロほどで東西の幅が1キロ弱ほどの沢と峰それに道に囲まれた少し変形した台形の山林となります。 25年3月18日 「岐小川=石山沢であった」 つい先日まで気づいていなかったのですが、数字だけではなく、もっと直接的に二つの図面の同一性を示す文字も記載されていました。字図では、現在は石山沢と呼ばれている牛滝川の支流は、岐小川と記されており、カッコ書きの中ではより丁寧に「宇志多岐小川」と記されています。そして、分筆登記に添付された10分の1の図面においても、この小川には「岐小川」との記載が付されているのです。私は、多分他の関係者も全員がそうであったと思いますが、過去においては、この『岐』という字は『枝』と同じように単に小さいもの小枝のようなものであることを強調する接頭語のようなもので「岐小川」は小川を意味する一般名詞に過ぎないと思い込んでいました。しかし、それがそもそも間違っていたのです。岐小川というのは紛れもない固有名詞だったのです。枝と岐は字としてはよく似ていますが、その意味や用法としては明らかに別物なのですが、ついその差異を見落としてしまっていたところです。 この事件にかかる判決文においても、分筆図面に記載された小川については「130番土地の東側境界線上には細い小川が記載(名称の記載ない)されており、・・・」と判示されています(参考に判決文の該当箇所を下記にリンクします。最終行にその記載があります)。『岐』という文字が川の固有名詞を意味しており(省略形ではあるが)、正に現在では「石山沢」と呼称されている小川そのものを意味していることに、これまで誰一人として気づいていなかったようなのです。牛滝川はこのヒバ林の袂で3つの支流に分かれており、それで、その一つの現在は石山沢を呼ばれる支流には「(宇志多)岐小川」との名称があてられていたわけです。なお、本流には「牛滝」の文字があてられているのに、この支流では「宇志多岐」の文字が使われているわけですが、この辺りの文字使いの相違については、坂井三郎氏にも全く分からないようです。事件と離れて、興味の沸くところです。 http://www.monobelaw.jp/material90006.pdf 25年3月19日 「部分林の謎と国有林の記載」 実は、この字図には、他にも重要な意味のある記載がなされています。一つは、図面の左手の少し下側にある「部分林」との記載です。そして、その部分林の範囲を示すように囲われた土地が示されています。部分林というのは、営林署と地元民が結ぶ協定書で、平たく言いますと、柴刈りの権利や植栽・伐採をして得た売り上げを一定割合で分け合うこと約した山林ということになります。不可解なのは、この部分林の記載場所が、坂井家が所有していたという堂の上の土地と重なるように思われる点です。字細間に所在し字牛滝川目との境界に接しており、まるで堂の上の土地のようなのです。この点は、三郎氏にも良く分からないようなのですが、私には、全てを把握していた17代源八が関わって作成された字図にこのような記載があるということは、堂の上の土地はそもそも坂井家の所有地ではなく部分林であった可能性が十分にあるように思われるところです。そうであれば、普段山に入って木々を取ることは出来ても、それは利用権に過ぎず、所有権の登記がないのは当然のこととなります。未登記以前の問題となります。 もう一つは、図面の左端の下隅の赤で塗られた部分の下にある記載です。「牛滝川目」との記載が6つあり、その横に、「右記官林区分」との記載が読み取れます。裁判資料からして、これらの記載は林野庁が主張する字牛滝川目に所在するとされる国有林の地番を示すものと考えて間違いないと思われます。とすると、この字図は、字牛滝川目に存在する広大な国有林を意識したうえで、広い坂井家の私有地を図示したものとなります。そうした状況からして、この字図は非常に客観性のある図面とみて間違いがないと思われるところです。 25年3月21日 「歴史の闇」 改めて分筆申請添付の図面を見ますと、字図同様に、ヒバ林が石山沢と官林峯と旧道で周囲三方を囲まれていることが明確に記されていることがよく分かります。そこに隠し事は一切なく、ただ、登記簿上の数値としてだけ当時の実測値の10分の1の値に変更していることが明々白々なのです。 このような大胆なことを17代源八が自分の考えだけで行ったとは到底考えられません。事前に役所それに営林署とも話をして、その様な対応で処理することの了解を得ていたものと思われます。恐らく、下北の現地では「これで手打ちが出来たもの」との理解であったのでしょうが(130番1を国有地とし、130番2を民有地とする)、結局は林野庁からのお墨付きが取得できず、紛争地としての状態が継続することになってしまったということのようです。なお、当時の測量が正しければ、実面積は登記面積の正確に100倍になるはずですが、さすがに明治中期の測量技術の未熟さから、佐藤測量士の実測面積は56倍ほどにとどまっているところです。 ただ、このことに関してある人が非常に不思議なことをメモに記しています。それは、「日露戦争を意識して、この辺りは本土防衛のための軍事機密地帯とされ、そこに民有地があることは陸軍にとって都合が悪かった。」ということだそうなのです。もちろんそれを裏付ける資料はありませんが、坂井家と林野庁の争いは、よくある実面積に比しての登記面積の狭小さということだけから生じた官民の土地争いではなく、もっと大きな政治的背景からの圧力がその裏にあったのかもしれません。そうだとすると、17代源八が地元営林署の了解を得たうえで妥協を図ろうとして分筆登記をしてもそれが問題の解決に結実しなかった理由が見えてくるように思います。地元営林署としては「それでよし」と判断して林野庁に承認を求めても、陸軍の意向も考慮せざるを得ない林野庁としては「ちょっと待て」と言わざるを得なかったのかもしれません。あるいはもっとひどくて、林野庁も事前にOKを出していたのだが、その後に陸軍が横槍を入れてきたのかもしれません。さすがにこうした話しはもう歴史の闇に消えてしまい今となっては確認のしようがないところです。 25年3月24日 「再度、査定図と登記・付属図面との関係」 3月5日の投稿で、AIの見解によれば明治の境界査定処分の結果は登記簿や付属地図に反映されたはずとのことでしたが、何となく気になったので、再度同じ質問を少し質問の仕方を変えて尋ねてみました。すると、今度は、「直接には影響しなかった」と見方によっては真逆に近い回答を得ることとなりました。どこまでいっても参考に過ぎないのですが、一応はAI自らが訂正したらしいので、その内容を下記お知らせします。
明治や大正時代の官民境界査定処分はその結果をどのように登記簿や土地台帳付属地図に反映させていたのですか?それとも、国との境界を当事者間で確定しただけで登記簿や付属地図には何ら影響しなかったのでしょうか? 回答 明治や大正時代の官民境界査定処分の結果は、登記簿や土地台帳付属地図に直接反映されていたわけではありませんでした。 官民境界査定処分は、国有地(官有地)と民有地の境界を確定する行政処分でした。この処分の結果は、主に以下の形で記録されていました。 したがって、官民境界査定処分は当事者間(国と民間所有者)で境界を確定しただけでなく、法的に有効な境界確定の効果を持っていましたが、その結果が直接的に登記簿や土地台帳付属地図に反映されることはありませんでした。ただし、後の測量や境界確定作業において、これらの査定結果が参照され、間接的に地図や登記情報に影響を与えた可能性はあります。 |
|||
| アーカイブ 2026年 2025年 2024年 2023年 2021年 2020年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 |
||||