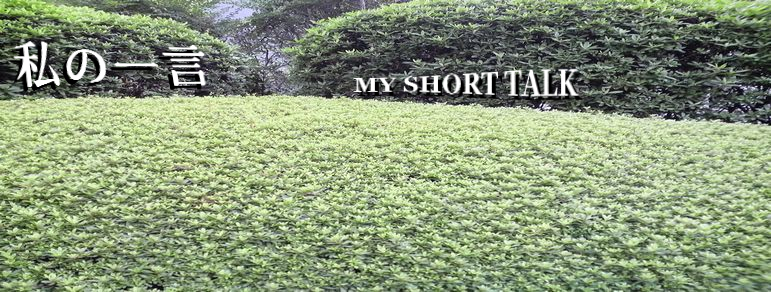 |
|||||
| |
|||||
| 公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の隠された謎に迫る) |
English |
||||
127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密(自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん―その2 2025/1/29 94.第三者委員会という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
本題に入る前に、簡単にヒバという木の素晴らしさを宣伝させて頂きます。私は、これまでヒバという名前は知っていましたが、それ以上の知識はなく、何となくヒノキの弟分的なものあるいはその2級品のように思っていました。多分、多くの人がそうなのではないでしょうか。木曽ヒノキと秋田スギのネームバリューが強すぎるわけです。青森ヒバは日本の3大美林の一つと言われながら、これまで明らかに格下扱いされてきたように思います。よくは知りませんが、価格でも他の二つと比較して下級に扱われているように思えてなりません。でも、この調査の過程で知ったのですが、ヒバという木はとんでもなく優れた樹種で、成長は極めて遅いのですがその分たいへん丈夫であり、水にも、火にも、害虫にも強く、建築資材として使えばほとんど何もしなくても何百年も持つようなのです。むしろ、江戸時代の方がヒバの価値が正当に評価され大切にされていた気がします。ほぼヒバで作られた平泉の金色堂は昭和の時代に大改修を受けるまで900年近くにわたり立派にその姿を維持していました。新しいところでは、太宰治の生家が有名なようですし、太宰自身も地元青森のヒバをたいそう誇りに思っていたようです。個人的には、最近話題の木材による高層建築などには最高の素材ではないのかと思うほどです(ただ、100パーセント素人の独り言ですが、直射日光に対する抵抗力が気になります)。 しかし、木材の利用促進が叫ばれウッドチェンジネットワークなる言葉も出回る中、そうしたことに絡んで「ヒバ」という言葉がほとんどマスコミに出ないことも不思議に感じられます。産地がほぼ青森県に限られており、過去の過剰伐採がたたってまるで絶滅危惧種のように扱われているからなのかもしれませんが、ことによるとこの「幻のヒバ林」の存在が影響しているのでは、とまで勘ぐってしまいます。そして、こんな素晴らしい木がこれまで大量に鉄道の枕木に用いられていたと聞くと、残念でなりません。本ヒバ林の現状と言い、この際ヒバという青森のそして日本が誇るべき樹種自体の復権・再評価を促したいと本気で考えています。法的なことの真相の解明は関係者にとって重大事ですが、このヒバ林に正当なスポットライトを与えることは社会的な重大事と言えそうです。そして、もし、私が家を建て替えることができるなら、にわかヒバ愛好家としてはその時は是非ともヒバを使いたいと思っています。 少し脱線が長くなりました。以下、本論に入ります。 明治27年の130番分筆の謎 私の手元に本ヒバ林の一部を空撮したと思われるカラー写真がある(別紙2)。誰が何時ごろ撮影したものなのか分からないのだが、恐らくは投資家の誰かの手により昭和50年前後に撮られたものと思われる。ほぼ全面くまなくヒバの青い葉っぱで覆われつくしている。見る人が見るとこの写真がとんでもなく立派なヒバ山の写真であることが分かるそうである。樹木の知識のない私には、そうした判断は出来ないのだが、このような一面のヒバ山、それも急峻な斜面、を一直線に二つに分けるなどと言う発想が一体どこから来るのだろうか、との疑問を持つための契機にはなる。このような山(斜面)では真っ二つには切りようがないのでは、との疑問である。実は、正にその様な非常に不思議なこと(分筆)が明治に生じてしまっておりそれにつき以下で説明したい。 ただ、この土地分筆はその後の紛争を予見しているほどの重要性があり、ここで本書の全体像・執筆の意図の概略を述べることしたい。それが読者の理解に必要と思われるからである。結論から言えば、昭和40年代からこのヒバ林の所有権をめぐってそれを国有林と主張する林野庁と元は坂井家が所有していた私有地であると主張する投資家の間で多くの裁判が争われ、奇妙な理屈(130番という地番の土地は本ヒバ林ではなく、そこから2キロほど北西の通称「堂の上」という所にある1万坪ほどの土地である)で林野庁がそれらの裁判で勝訴したことから(罠にはまった裁判)、事実上本ヒバ林は坂井家の手を離れ、今では国有林との扱いを受けているのだが、そうした裁判が完全な間違いによるものであることを明らかにするのが本書の眼目となっている。それなら裁判をやり直せばと思われる読者もおられるであろうが、技術的な難しさの他に、そもそも(民事の)裁判所というところは真相を明らかにするための場所ではなく、むしろ、真相にふたをするのがその実態であることから、公のすなわち世の判断を得るためにこのように公開記事に訴えることとなったものである。目的は二つ、ことの真相を明らかにすることと、隠されたままの日本一のヒバ林を世にデビューさせることにある。 なお、また少し本題からそれて恐縮だが、この日本の裁判所の持つ致命的欠陥については愚痴を言い出すと切りがなく、もし関心がおありであれば、「和を以て貴しとせずーその2」でネット検索いただきたい。今の我が国の裁判所の欠陥を取り上げている。 国が当事者の裁判で大間違いがあったなどと言っても誰もすぐには信じられないであろうが、そのあり得ないはずの間違いが生じてしまったのが本件であり、最後までお付き合いを願いたい。では、早速、その不思議な分筆の物語に入ることとする。 明治27年になり、17代源八は、その目的は定かでないのだが、本ヒバ林を測量した上で、それを130番1と130番2の二つの土地に分筆している。そして、測量の結果に基づいた分筆としながらもその登記申請では実際の面積よりはるかに小さく130番1の面積を約1町とし、同2の面積を2町強とし、土地台帳付属地図上でもそのような大きさのものとして修正がなされている(全体では約1万坪の広さとなる)。私にとっては、このような不可解な実態を示さない分筆登記が何故なされたのかが当初から大きな疑問であった。元の1反6畝2歩からするとかなり広くなったのだが、後に述べる本来の山の面積からはかけ離れた小ささなのである。とにかく中途半端な訳である。どうしてもこの謎が解けず、私はずーとヤキモキしていたのだが、一昨年になって、ようやくこの分筆の際の測量の実測値を示すであろう書面を入手することができた。坂井氏が自宅で保管していた資料箱から見つけ出したのである。それによるとこの分筆の登記面積は実際の測量で得られた距離の正確に10分の1の数値に基づき計算されたものであることが判明したのだ。ということは、分筆の際の測量が正しければ、実際の面積は分筆登記面積の100倍の広さ(約100万坪)があることとなるのだが、この点は後に触れるように測量技術の稚拙さからかなりの誤差が生じていたことが知られることとなる。 このような登記簿上の面積と実際の面積の差異は、やはり、租税の高騰を恐れてのことと推察されるが、17代源八は、村役場には実際の距離を示す測量図を提出しており、それを基に村役場により本ヒバ林の所在とその大きさが明記された図面が作成されたわけである(資料4「字牛滝川目の字界図」)。この図面によると、本ヒバ林は、北側を牛滝部落から野平へ通じる旧道に接し、東側を石山沢に接し、西ないし南を山の峰で区画された東向きの広大な斜面であることが知られる。税務署や登記所には10分の1の距離で申告し、地元の村役場には正しい図面を提出していたというわけである。このことは、裁判で証拠として提出された分筆登記申請書に添付された測量図面に記載の数値が資料4の字界図に記載された数値のピッタリ10分の1であり、また形状もそっくりであることから疑いの余地がないところである(資料5「分筆申請書と添付の測量図」)。多くの村人にとっては、役所関係者を含め、石山沢のヒバ林は従前から坂井家のものであったわけであり、その登記簿上の面積数値は単に表向きの形作りといったものであったようなのである。 ただし、私は、分筆申請に添付された測量図を見た時、「一体この直線的な切り方は何を意図して分筆しようとしたのかさっぱりわからない。どこか別の土地ではないのか?」と不思議に思ったことを覚えている。宅地や畑なら、また林野でも平たんな土地なら、自分の気に入ったように分けることもできるだろうが、急峻な斜面になっている山を分ける際にはその地形を無視した分け方はむつかしいはずであり、現地に精通していない私が考えても本分筆添付の図面は不思議な分け方なのである。 この字界図自体は、その体裁からして村役場の手になるものであることは間違いがないようである。村役場は、17代源八から明治27年の分筆に際して作成された実際の測量図の提出を受けて元からある字牛滝川目の字界図に私人の所有地ではあるが130番の1と2を付け足したものと思われる。一見して分かるように、この地番の土地は単独で字牛滝川目全体の面積の10分の1程度を占めるような広大さであり、牛滝川目の字界図に特記するに足る重要性を有していたものと思われる。そして、この地番の西側と南側の境界線付近には「官林峯」との記載まである。要は、西と南を国有林に、北を旧道に、東を石山沢に囲まれた東向きの山の斜面全体がこの地番の対象であることが一目瞭然なのである。ただ、そこでは石山沢との表記に代えて「宇志多岐小川」との記載がある。何故このような表記となっているのかについてはいまだ確認ができていないのだが、それが石山沢を指すことに何の疑問もないところである。枝小川というのは支流であることを意味するものと思われるが、牛滝に代えて「宇志多岐」という文字が当てられているわけは不明なのである。 それにしても、何故、17代源八がわざわざ多額の費用をかけてこの広大な山を測量しヒバ山を二つに分筆しようとしたのか、そして、その登録に際しては2面性を持たせて表向きは実態を示さないような面積で登記申請をしつつ、半ば仲間内と思われる村役場には実態を示す測量図を提出したのかが大きな疑問となる。ここから先は推測に頼るしかないのだが、当時からこのヒバ林を巡っては坂井家と林野庁との間でその境界につき争いがあり、その解決策として17代源八はヒバ林を二つに分けて、そのどちらかを国有林として認めることで争いの手仕舞いを図ろうとしたのではないか、と私には思われる。処分する意図もないのに多額の費用をかけてまでこのような測量・分筆登記をすることは考えられず、また、処分先としては、林野庁しか考えられないところだからである。もし民間人に売却する意図があったのなら、せめてその売却対象となる筆(地番)部分の土地面積は実測面積そのもので登記がなされたはずであり、それがなされていないということは民間人への譲渡は意図されていなかったと判断する他ない。 そう考えると、17代源八が現地の地形に一切考慮を払わずに直線的に1:2の面積比でこのヒバ林を二つに分けた意図が理解できるように思われる。「とにかくこれで林野庁との関係にケリをつけたい。すっきりできるなら山の3分の1は林野庁に譲っていい」との思いでの分筆であったように思われるのである。もっと言えば、ここまでのことを17代源八が一方的に実行に移すとは思われず、その当時にほぼこのような妥協点が地元営林署との間にできていたとすら想像される。しかし、それが、よくあることだが、中央省庁の了解がもらえず、断ち切れになった可能性が高い。 実は、この字界図にはもう一つ重要な情報が隠されている。それは、図面の左下の赤で色塗りされた箇所のすぐ下にある字牛滝川目の地番らしき記載とそれにつき付された「右記官林区分」との記載である。残念ながら私が手に入れた字界図は坂井家が保管していた書類の中から見つけたもので、その体裁からして比較的最近(平成?)になって実物の主要部をカラーでコピーしたものと思われる。その際、赤塗された部分が見えないように処理されたと思われるし、図面の下部の記載はコピー対象から省かれてしまったようで、完全なものではない。ただ、裁判において林野庁は一貫して以下の地番が国有林であると主張し、その土地台帳を証拠提出している。 字牛滝川目135番 1620町 字牛滝川目137番 720町(この一部がヒバ林との主張) 字牛滝川目141番 864町 字牛滝川目142番 1296町 字牛滝川目143番 1296町 こうした裁判における林野庁の主張を考慮すると、字界図の左下の記載は、これらの国有林を指しているものと考えて間違いないと思われるところであり、そうだとすると、この字界図が作成された当時少なくとも村役場では国有林とは別途に坂井源八が石山沢沿いに広大な山林を所有しているとみなしていたことが知られるはずである。この字界図の原本かその全面コピーが入手できればより明確になるのだが、私が昨年佐井村役場に尋ねたところでは「そのような図面は(現在役場では)所持していない」との回答を受けている。一体いつ誰が何処へ持ち出したのか、気になるところである。 また、そもそも国有林に付された地番、それも私有地の地番と連番のような地番、が課税台帳である土地台帳に登録されていること自体不可解に思えるところであるが、加えて、上記の土地5筆を合わせた面積が5796町にもなる。約1700万坪という広大さである。普通、ゴルフ場を開設するには50万坪ほどが必要とされているから、ゴルフ場34個分に匹敵するような広大な面積ということになる。字牛滝川目の広さがどのくらいあるかは知らないが、字界図から視覚的に判断する限り、そこまでの広さがあるとは到底思えないところである。このあたりのことは、今後必要があれば調査確認することになる。 ―続く― |
||||
| アーカイブ 2026年 2025年 2024年 2023年 2021年 2020年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 |
|||||